ベンダー資格(民間資格)のおすすめは?エンジニアが取得するメリットや勉強のコツも解説

エンジニアとして働くなかでスキルを証明する資格を取りたいが、どれを選べばよいかわからないと悩んでいませんか。
国家資格は難易度が高く時間もかかる一方、ベンダー資格なら実務に直結した技術力を効率的に証明できます。
本記事では、民間のベンダー資格の特徴・国家資格との違い・おすすめの資格6選・取得のメリットやデメリットを詳しく解説します。
さらに資格選びの基準や効果的な勉強方法も紹介するので、自身に合う資格を見つけてキャリアアップにつなげてください。
目次
ベンダー資格(民間資格)とは

ベンダー資格とは、マイクロソフト・オラクル・AWSなどのIT企業が自社製品やサービスに関する知識や技術を認定する民間資格です。
国家資格が汎用的な知識を問うのに対し、ベンダー資格は、特定技術に特化した実践的スキルを証明できる点が大きな特徴です。
企業では即戦力として評価されやすく、分野特化のスペシャリストを目指すエンジニアにとって重要な資格となるでしょう。以下では、特徴や国家資格との違いを解説します。
ベンダー資格の特徴
ベンダー資格の大きな特徴は、実務で使用する製品やサービスに関する専門知識を体系的に学べる点です。
資格取得を通じて新しい技術の動向を把握でき、バージョンアップに合わせた更新制度により常に現場で通用するスキルを維持できます。
また、世界共通で通用する資格も多く、グローバルな技術力の証明にもなります。ただし有効期限のある資格も多く、定期的な更新が必要な場合もあるため注意が必要です。
企業によっては資格手当や報奨金制度を設けているケースもあり、収入アップにつながる可能性もあります。
国家資格との相違点

国家資格とベンダー資格の大きな違いは、認定機関と対象範囲です。
国家資格は経済産業省が認定し、ITの基礎知識や理論を幅広く問うのに対し、ベンダー資格は各IT企業が自社製品に特化した実践的スキルを認定しています。
基本情報技術者試験などの国家資格は体系的な学習が必要な一方、ベンダー資格は実務経験があれば短期間で取得可能なものも存在します。
また、国家資格は取得すれば永久的に有効ですが、ベンダー資格は2〜3年程度の更新が必要なケースが少なくありません。
両資格とも企業の評価は高く、組み合わせて取得すれば、総合的な技術力をアピールできるでしょう。
エンジニアに資格は必要?

エンジニアに資格は必須ではありませんが、キャリア形成にとって重要な役割を持ちます。
実務経験だけでは証明しにくい知識を客観的に示せるため、転職や年収交渉で有利に働くケースがみられるでしょう。
特に未経験分野への挑戦時や上流工程を目指す際には、資格が技術力の裏付けとなります。また資格取得で得た知識は、実務での問題解決能力の向上にも役立ちます。
社内評価の昇進・昇給の判断材料としても活用されるでしょう。
ただし資格取得が目的にならないよう、自身のキャリアプランに沿った資格を選択し、実務経験と組み合わせることが大切です。
私たちテクニケーションでは、ベンダー資格を活かしてキャリアアップしたいエンジニアを全力で応援しています。
案件単価の全面開示と単価給与連動制により、資格で身につけた専門スキルが市場で評価されれば、適正に報酬へ反映される透明性の高い評価制度です。
案件選択制度で、自身のスキルに合った案件を選べるため、資格を実務で活用しながら経験値を高められます。
チーム単位での活動により、メンバー同士で知識を共有し、互いに成長できる環境も魅力的です。
今の環境に限界を感じている方、もっと成長したいと考えている方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、自身の想いをお聞かせください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
ベンダー資格のおすすめ6選

多数あるベンダー資格のなかから、特にエンジニアのキャリアアップに役立つ6つを厳選して紹介します。
初心者から上級者まで段階的にスキルアップできる資格や、需要が高まる分野中心の選定です。どれも実務での即戦力を証明でき、多くの企業で高く評価されています。
それぞれの特徴や難易度、活用場面にも触れます。
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
MOSはWord・Excel・PowerPointなどMicrosoft Office製品の操作スキルを証明する世界標準資格です。
エンジニアにとって基礎的な資格で、書類作成の効率化や新人研修の修了証明にも利用されています。
試験は実技形式で、アソシエイト(一般)とエキスパート(上級)の2レベルがあり、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。
合格率は約80%あり、1〜2ヶ月の学習で取得が可能です。特にExcelのマクロやVBAも扱えれば、データ分析や業務自動化などさらに付加価値を高められます。
オラクルマスター(ORACLE MASTER)

オラクルマスターは、世界トップクラスのデータベースOracle Databaseの技術力を認定する資格です。
Bronze・Silver・Gold・Platinumの4レベルがあり、段階的に実力を伸ばすことができます。
データベース管理者やバックエンドエンジニアには特に重要で、SQLの基礎から障害対応、パフォーマンスチューニングなど幅広い知識が習得可能です。
Silverレベル以上は世界共通資格として認められ、グローバル企業でも高評価です。初級Bronzeは2〜3ヶ月の学習が目安で、実機での演習が重要となります。
AWS認定資格
AWS認定資格は、Amazon Web Servicesのクラウドサービスに関する知識とスキルを証明する資格体系です。
基礎レベルのクラウドプラクティショナーから、アソシエイト・プロフェッショナル・専門知識の4段階があります。
クラウド移行が進むなか、ソリューションアーキテクトなどは特に需要や年収アップへの効果が高い資格です。試験は3年ごとの更新制で、常に新しいクラウド技術を学べます。
初心者はクラウドプラクティショナーから始め、1〜2ヶ月の学習で合格を目指せます。実務経験を組み合わせれば、市場価値もさらに高まるでしょう。
Linux技術者認定試験(LinuC)

LinuCは、日本市場向けのLinux技術者認定資格でLPI-Japanが運営しています。レベル1から3まで段階的に学べ、サーバー構築や運用管理などのスキルを証明できます。
LinuxはWebサービスやクラウド環境の基盤として広く使われ、インフラエンジニアには重要な知識です。
レベル1は基本コマンド操作やシステム管理を中心に、実務未経験でも3〜4ヶ月で合格可能です。
仮想環境での実機演習も大切で、資格取得後はクラウドエンジニアやSREなどへのキャリアパスが広がります。
シスコ技術者認定
シスコ技術者認定は、ネットワーク機器世界大手のシスコシステムズが提供する資格体系です。
CCNA(エントリー)・CCNP(プロ)・CCIE(エキスパート)の3段階があり、特にCCNAはネットワークエンジニアの登竜門として有名です。
技術内容として、TCP/IP・ルーティング・セキュリティの基礎が習得できます。試験は3年ごとの更新制で、新しい技術の動向に対応しています。
CCNAは3〜6ヶ月が学習目安で、シミュレーター活用の実機演習が合格の鍵となるでしょう。
Google Cloud認定資格
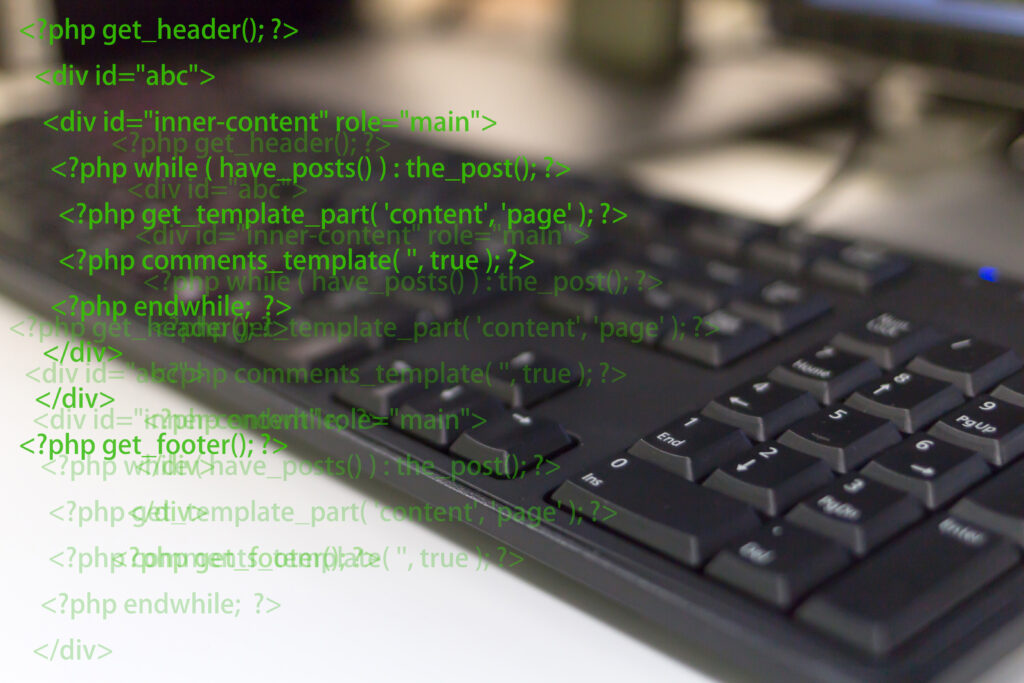
Google Cloud認定資格は、Google Cloud Platform(GCP)の技術を証明する資格体系です。
Cloud Digital Leader・アソシエイト・プロフェッショナルまでレベルが幅広く、特にデータ分析や機械学習分野の資格は市場価値が高いとされます。
試験は2年ごとの更新制で、Googleの新しい技術をキャッチアップできる仕組みです。
初心者向けのCloud Digital Leaderは1ヶ月ほどの学習で合格可能で、GCPの基本概念を理解する入り口として適しています。
エンジニアがベンダー資格を取得するメリット

ベンダー資格の取得は、エンジニアのキャリアに具体的なメリットをもたらします。
技術力の客観的な証明となるだけでなく、企業内での評価向上や転職市場での競争力強化にもつながるでしょう。
資格手当による収入増加や、プロジェクトへのアサイン優先度の向上など、実利的な効果も期待できます。
以下では、専門スキルの証明と昇進・キャリアアップへの影響について詳しく解説していきます。
専門的なスキルの証明になる
ベンダー資格は、特定の技術領域の専門性を客観的に証明する強力なツールです。
実務経験だけでは伝わりにくい技術的な深さや体系的な知識を、第三者機関の認定という方法で可視化できます。
例えばAWS認定を持つエンジニアは、クラウドアーキテクチャの設計能力を明確に示せるため、プロジェクトへの参画機会が増加します。
また顧客や取引先への提案時にも、資格保有者がチームにいることで技術的な信頼性が高まり、受注率の向上にもつながるでしょう。
転職活動では書類選考の通過率が大幅に改善し、特に未経験分野への挑戦時には強力な武器となります。
グローバル企業では世界共通の評価基準として機能するため、海外プロジェクトへの参画チャンスも広がるでしょう。
昇進・キャリアアップの評価材料になる
多くの企業では、ベンダー資格を昇進や昇格の評価項目として明確に位置づけています。
人事評価制度に資格取得を組み込む企業が増えており、管理職への昇進条件として特定資格の取得を必須とするケースも見られます。
資格手当として月額5,000〜30,000円を支給する企業も多く、複数資格の取得で年収が500,000円以上アップした例も珍しくありません。
また資格取得は自己研鑽への意欲の表れとして評価され、プロジェクトリーダーやアーキテクトなど上流工程への配置転換のきっかけにもなります。
社内公募制度でも資格保有者が優遇される傾向にあり、希望部署への異動が実現しやすくなるでしょう。
さらに資格更新のための継続学習が新しい技術のキャッチアップにつながり、長期的なキャリア形成にも寄与します。
一般的なSES企業では案件単価が非公開で、エンジニアの取り分は3〜4割程度に留まることがほとんどのなか、テクニケーションは高い還元率を実現しています。
ベンダー資格で身につけたスキルが市場で評価されれば、その価値がダイレクトに報酬へ反映される透明性の高い仕組みです。
さらに案件選択制により、取得した資格を活かせるプロジェクトを自ら選択でき、主体的にキャリアを形成できるでしょう。
チーム制サポートも採用し、現場での孤立もありません。報われない評価や還元率に不満を感じている方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、新しい働き方を検討してみませんか。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
エンジニアがベンダー資格を選ぶデメリットはある?

ベンダー資格にはいくつかのデメリットも存在します。まず更新制度により2〜3年ごとに再受験や更新料が必要となり、継続的なコストが発生する点は見逃せません。
また特定製品に特化しているため、その技術が陳腐化したり企業が別製品に移行したりした場合、資格の価値が低下するリスクもあります。
国家資格と比較すると認知度が低い資格もあり、企業によっては評価されないケースも存在するでしょう。
受験料も1回あたり5,000〜50,000円で、上位資格になるほど費用負担が大きくなります。
ただしこれらのデメリットを理解したうえで、自身のキャリアプランと照らし合わせて戦略的に選択すれば、投資対効果の高い資格取得が可能です。
ベンダー資格の取得がおすすめなエンジニア
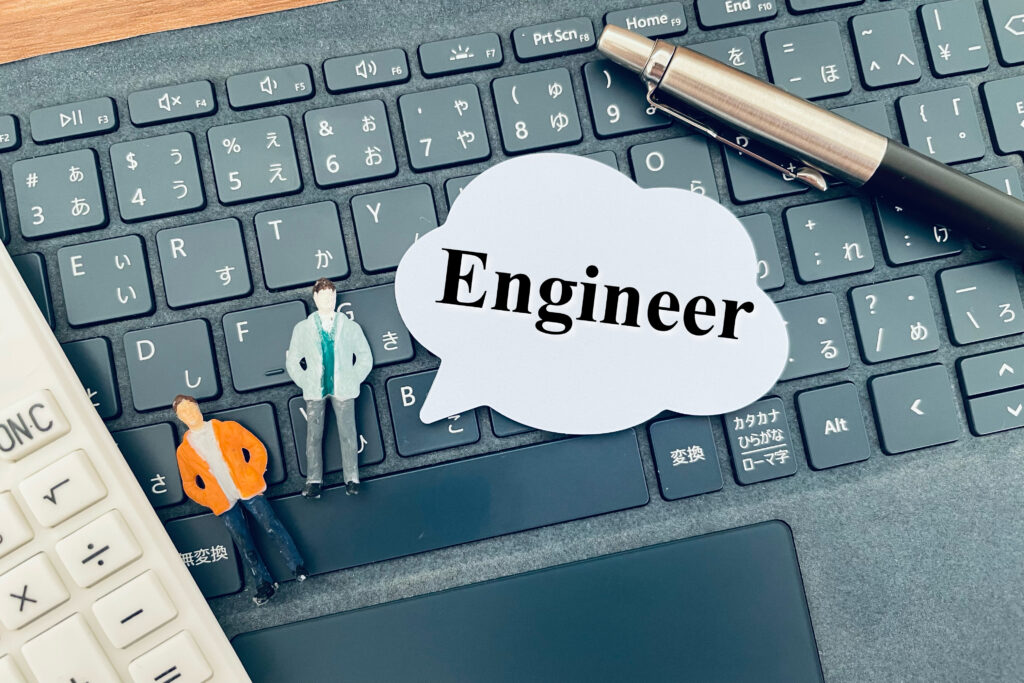
ベンダー資格は職種によって求められる資格が異なり、適切な選択が重要です。
インフラエンジニアはサーバーやネットワークの構築・運用に関わる資格、システムエンジニアはアプリケーション開発やプロジェクト管理に役立つ資格が推奨されます。
それぞれの職種で評価される資格を把握し、自身の業務内容や将来目指すポジションに合わせて取得すれば、効果的なスキルアップが実現できるでしょう。
インフラエンジニア
インフラエンジニアには、サーバー・ネットワーク・クラウド基盤に関するベンダー資格が強く推奨されます。
LinuCやLPICでLinuxの運用スキルを証明し、CCNAでネットワークの基礎を固めることが第一歩となるでしょう。
後に、AWS認定やAzure認定などクラウド系資格の取得により、オンプレミスからクラウドまで幅広く対応できるエンジニアとして市場価値が高まります。
特に近年はインフラのコード化が進んでいるため、TerraformやAnsibleなどのツールに関する認定も注目されています。
システムエンジニア

システムエンジニアは、開発言語・データベース・プロジェクト管理に関するベンダー資格が有効です。
オラクルマスターでデータベース設計力を証明し、Java認定資格やMicrosoft認定資格で開発スキルをアピールできます。
上流工程を担当する場合は、PMPやスクラムマスター認定などプロジェクト管理系の資格も重要になるでしょう。
また近年では、DevOpsエンジニア認定やセキュリティ関連のCISSPなど、開発プロセス全体を俯瞰できる資格の需要も高まっています。
特にアジャイル開発が主流のなか、スクラムマスター資格を持つことでチームリーダーとしての価値も向上するでしょう。
ベンダー資格を取得してスキルアップした方には、私たちテクニケーションの環境が適しています。
テクニケーションでは単価給与連動制を採用しているため、案件単価に応じて年収アップを目指すことができます。資格による技術力の向上が適正に評価されやすく、報酬に直結する透明性の高い仕組みがあります。
また案件選択制により、興味のある分野や資格を活かせるプロジェクトを自ら選択でき、主体的なキャリア形成が可能です。
エンジニア経験者が創業した会社だからこそ、現場の課題を理解したエンジニアファーストの制度設計を実現しています。
資格を活かしてキャリアアップしたい方は、私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談にて、自身のキャリアビジョンをお聞かせください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
取得を目指すベンダー資格の選び方

数多くのベンダー資格から適切なものを選ぶには、明確な基準を持つことが重要です。
将来のキャリアビジョンから逆算する方法や自身の興味関心を軸にする方法、現実的な難易度や費用を考慮する方法など、複数の視点から検討して合格を目指します。
闇雲に人気資格を取得するのではなく、自身の状況に合った戦略的な選択が、効果的なスキルアップとキャリア形成につながるでしょう。
将来のキャリアパスから逆算して選ぶ
5年後、10年後になりたいエンジニア像を明確にし、そこから逆算して必要な資格を選ぶことが重要です。
例えばクラウドアーキテクトを目指すなら、AWS認定ソリューションアーキテクトから始め、段階的にプロフェッショナルレベルを目指します。
プロジェクトマネージャーを志向するなら、技術系資格に加えてPMPの取得が必須となるでしょう。
転職市場の求人要件を分析し、目標ポジションで求められる資格を優先的に取得することで、着実にキャリアアップへの道筋をつけられます。
興味のある分野から選ぶ

自身が興味を持てる技術分野の資格から始めることで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。
インフラに興味があればLinuCやCCNA、データ分析に関心があればGoogle Cloud認定データエンジニアを選択しましょう。
セキュリティに魅力を感じるならCISSPやCompTIA Security+が候補となるでしょう。
興味のある分野なら実務でも積極的に関われるため、資格の知識と実践経験の相乗効果が期待できます。
また、業界のトレンドや新しい技術に自然と触れる機会も増え、継続的な成長につながります。
難易度と学習コストを比較して選ぶ

現実的な学習時間と費用を考慮して資格を選ぶことも重要です。
初心者なら合格率60%以上のMOSやAWS Cloud Practitionerから始め、段階的に難易度を上げていくのが賢明でしょう。
受験料は5,000〜50,000円と幅があり、上位資格ほど高額になる傾向があります。
また学習期間も1ヶ月から1年以上と資格により大きく異なるため、仕事との両立を考慮した現実的な計画が必要です。
企業の資格取得支援制度を活用できれば、費用負担を軽減しながら効率的に学習を進められます。
ベンダー資格でスキルアップしたのに、年収が上がらない悩みはありませんか。
私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりのキャリアを大切にし、資格による市場価値を報酬へ反映させる仕組みを構築しています。
また、チーム単位での活動により、資格の知識を実践で活かしながら仲間と切磋琢磨できる環境が整っています。
案件単価を隠さず開示し、単価給与連動制で透明性の高い評価制度を実現しているため、納得感を持って働きやすい点も魅力です。さらに案件選択制を導入しているため、取得した資格を活用できるプロジェクトを自ら選択し、実務経験を積むことが可能です。
ベンダー資格の取得を通してキャリアアップを実現したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、新しいキャリアの可能性を探ってみませんか。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
ベンダー資格に合格するための勉強のコツ

効率的な学習方法の確立が、ベンダー資格合格の近道です。独学で挫折した方も、目的の明確化・計画的なスケジュール設定・適切な教材選びができれば合格に大きく近づけます。
仕事と両立しながら実践できる具体的な勉強法を説明するので、自身に合うスタイルを見つけて合格を目指しましょう。
資格取得の目的を明確にする
目的の明確化により学習のモチベーションが維持でき、効率も上がります。転職で収入アップやプロジェクトリーダーを目指すなど具体的な目標を設定しましょう。
明確な目的があれば、必要な知識に集中でき不要な学習を減らせます。資格取得後のキャリアパスも想像し、目標達成の期限を決めて逆算し計画的に進めることが大切です。
周囲に資格取得を宣言すれば、適度なプレッシャーで学習の継続性も上がります。
学習スケジュールを立てる

学習計画は週・日単位で具体的に管理しましょう。試験日から逆算して計画を立てるのが効果的です。
平日は1〜2時間、休日は3〜4時間の勉強時間を確保し、3ヶ月程度で合格を目指すのが現実的です。
進捗管理アプリやカレンダーで学習状況を見える化し、定期的に模擬試験で理解度をチェックします。
計画どおりに進まない場合のバッファも作るとよいでしょう。生活リズムに合わせて学習時間を設定し、習慣化すれば継続できます。
自身に適した教材・学習ツールを用いる
学習スタイルに合う教材を選ぶことが効率化のポイントです。動画教材やオンライン講座は視覚的に学びたい方、公式テキストや問題集は体系的に学びたい方向けです。
実機演習が必要ならクラウドやシミュレーターを活用しましょう。スマートフォンアプリを使った、通勤時間の有効活用も効果的です。
まずは無料の公式資料から始め、難しい部分のみ有料教材で補完すると費用対効果も高いとされます。
オンラインコミュニティで仲間と情報交換し、疑問解決やモチベーション維持に役立てましょう。
資格に悩んだらスキルアップ支援を重視して転職するのもあり

資格取得を目指すエンジニアには、企業のスキルアップ支援制度が大事です。
受験料・教材費の負担・業務時間内の学習許可・報奨金など充実した支援を導入する企業が増えています。
現職で資格が評価されず学習時間の確保が難しい場合は、支援が手厚い企業への転職も選択肢となるでしょう。
社内勉強会やメンタリングなどがあれば、独学では得られない実践的知識も身につきます。
転職時には資格支援制度の内容を確認し、自身の成長を後押しする企業を選ぶことでキャリアアップも加速できます。
ベンダー資格を取得してキャリアアップを目指そう

ベンダー資格は、エンジニアのキャリアアップを実現する強力なツールです。
実務に直結した専門知識を体系的に学べ、技術力を客観的に証明できるため、転職市場での評価向上や年収アップにつながります。
MOSのような基礎的な資格から、AWS認定やGoogle Cloud認定などの新しいクラウド技術まで、自身のレベルや目標に応じて段階的にスキルアップできるのも魅力でしょう。
資格取得で得られる知識は実務での問題解決力を高め、継続的な学習習慣も身につきます。
まずは自身のキャリアビジョンを明確にし、希望に合った資格を選んで一歩踏み出してみてください。
フリーランスの高収入は魅力的だが、不安定さがネックという方にこそ、私たちテクニケーションの働き方がおすすめです。
正社員として安定した雇用を保ちながら、単価給与連動制により市場価値に見合った高い報酬を実現できます。
ベンダー資格で培った専門性が適正に評価され、努力がしっかりと収入へ反映される案件へ参入できる仕組みが整っています。
また案件単価を100%開示する透明性や資格を活かせる案件を選べる自由度、チーム制による万全のサポート体制など、エンジニアが希望する環境が用意されている点が特徴です。
従来のSES企業とは一線を画す新しい働き方に興味がある方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談でお話しましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!





















