SES(客先常駐)で退職を引き止められたら | 起こりやすいトラブルと対処法、途中退職の注意点も解説

SES企業を退職しようと考えたとき、トラブルになったらどうしようと不安を抱く方は少なくありません。
客先常駐は、自社だけでなく常駐先との契約関係やプロジェクト進行状況が絡むため、退職の意思を伝えるだけではスムーズに進まないこともあるでしょう。
本記事ではSESを退職する際の基本的な流れから、引き止めやトラブルが起こる理由、その具体的な対処法までを解説します。
さらに、契約・法律面で注意すべきポイントや、プロジェクト途中で退職をする際に必要な行動指針も紹介しています。
この記事を最後まで読めば、退職に関する法的な権利や実務上の注意点が明確になり、自信を持って計画的に行動できるようになるでしょう。
目次
SESを退職する際の流れ

SESからの退職を成功させるためには、感情や勢いに任せるのではなく、定められた手順に沿って計画的に進めることが重要です。
正しい流れを理解し、一つひとつのステップを丁寧に進めれば、不要なトラブルを未然に防ぎながら円満な退職を実現できます。
ここでは、退職を決意してから実際に退職するまでの基本的な流れを3つのステップに分けて解説します。
就業規則と業務内容を確認する
退職を決意したら、まずは会社の就業規則や雇用契約書を確認しましょう。
1ヶ月前や3ヶ月前など退職の申し出期限や、契約更新のタイミング、残っている有給休暇の扱いなどを事前に把握しておくことが重要です。
期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条では退職の申し出から2週間で、雇用契約は終了すると決められています。
しかし、円満な退職とスムーズな引継ぎのためには、会社の就業規則に従うのが一般的です。まずはこの規定を確認し、退職日から逆算してスケジュールを立てましょう。
現在参画しているプロジェクトの契約期間や業務内容もチェックし、退職時期までに引継ぎができるようにしておくことも重要です。
直属の上司に退職の意思を伝える

次は直属の上司に退職の意思を伝えます。先に人事部や常駐先の担当者に連絡するのではなく、まずは日々の業務で直接関わっている上司に報告するのが基本です。
円満な退職のために、報告の順番は守るようにしましょう。
「ご相談があります」と切り出し、会議室などほかの方に聞かれない場所で、1対1で話す時間を設けてもらうのがマナーです。
メールやチャットで一方的に伝えるのは避けましょう。理由は簡潔かつ前向きに伝え、退職の時期も具体的に示しておきます。
この段階で感情的にならず、淡々と事実を伝えることで、不要な引き止めや対立を避けやすくなるでしょう。
業務を引き継ぐ
退職が正式に承認されたら、最終出社日までの期間で後任者への業務引継ぎを行います。
上司と相談しながら、誰に何をいつまでに引き継ぐのかを明確にしたスケジュールを作成しましょう。
担当しているタスクやプロジェクトの進捗状況、関係者の連絡先や使用しているツールなどを整理し、後任者がスムーズに業務を続けられる状態にします。
退職後も後任者が一人で業務を遂行できるレベルの詳細な資料を目指しましょう。
最後まで責任を持って業務を完了させる姿勢が、円満退職への近道です。
SES(客先常駐)の退職を引き止められる理由
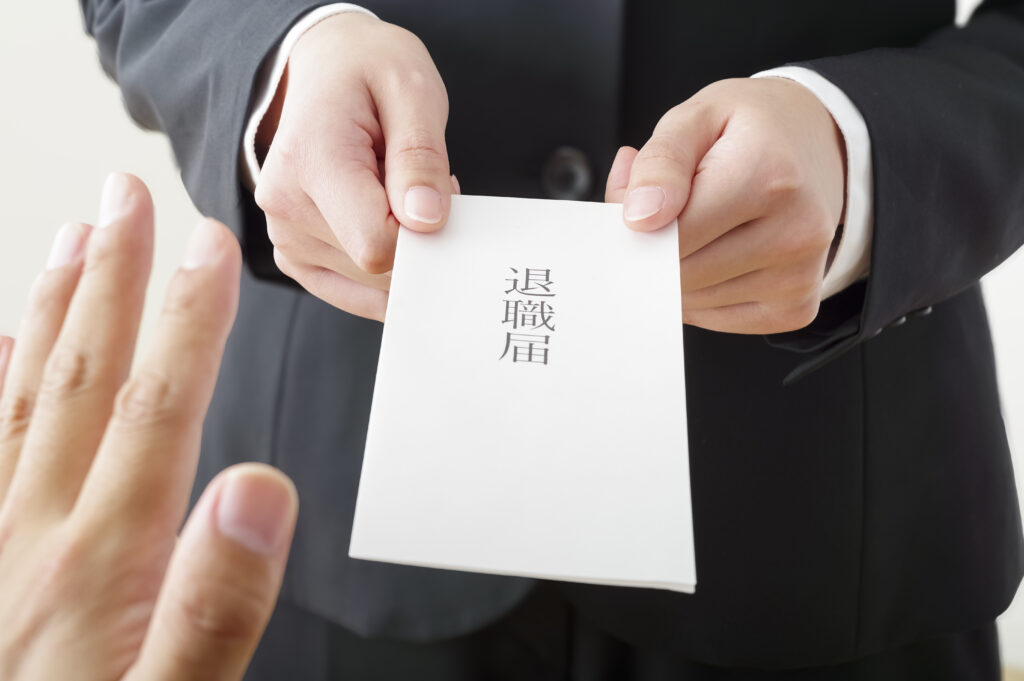
退職の意思を伝えた際、多くのエンジニアが経験するのが引き止めです。
情に訴えられたり、待遇改善を提示されたり、ときには厳しい言葉を投げかけられたりするケースもあります。
企業がそこまでしてエンジニアの退職を引き止めようとするのには、SES業界特有の事情があります。
引き止めの理由を客観的に理解すれば、感情的にならず、冷静に対処できるようになるでしょう。
まず、SESは常駐先との契約を継続するために一定の人員を確保する必要があり、急な退職は契約違反や評価低下につながるリスクがあります。
また、担当者が抜けることでプロジェクトが中断・遅延する可能性があり、それによって損失や信頼低下が発生するケースもあるでしょう。
さらに新たに人材を募集し、教育するには時間とコストがかかるため、企業側はできるだけ現状維持を希望します。
こうした背景を理解しておけば、引き止められても感情的にならず、冷静かつ建設的に退職交渉を進められるはずです。
SES(客先常駐)の退職で起こりやすいトラブル

円満な退職を目指していても、残念ながらトラブルに発展してしまうケースもあります。
特にSES業界では、自社と常駐先との板挟みになりやすいため、特有のトラブルが発生しがちです。
ここでは、実際に起こりやすい代表的なトラブルを3つ紹介します。事前に知識として持っておくと、万が一の際にも冷静に対処できるでしょう。
退職までの期間を一方的に延長される
就業規則や労働契約で定められた退職予告期間を守って申し出たにもかかわらず、一方的に退職日を延長されることがあります。
希望どおりの日程で退職させてもらえないのは、次のようなケースです。
- 後任がみつかるまで待ってほしい
- プロジェクトの区切りまでは辞めさせられない
- 常駐先との契約が切れる月までは退職できない
会社側の事情もあるのは当然ですが、法的には会社の都合で労働者の退職を不当に妨げることはできません。
民法第627条によると期間の定めのない雇用契約であれば、労働者はいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間経過すれば契約が終了します。
とはいえ、現場の事情を盾に引き止められるケースは少なくありません。
有給休暇を使わせてもらえない

退職日までの期間中、残っている有給休暇を消化したいと申し出た際に、拒否されるトラブルも頻発します。
- 引継ぎが終わっていないと使えない
- 人手不足だから難しい
- 最終出社日までしっかり働いてほしい
上記の理由での有給休暇の取得拒否は、労働基準法第39条に違反する行為です。
有給休暇は、労働者に与えられた正当な権利であり、会社側には原則として取得を拒否する権利はありません。
会社は、事業の正常な運営に支障がある場合に限り、従業員の取得日を変更できる時季変更権があります。
ただし、退職日がすでに決まっていてほかに取得可能な日がない労働者に対して時季変更権を行使すると、事実上権利を消滅させることになるため原則認められません。
損害賠償請求をほのめかされる
退職の意思が固いとわかると、会社側が態度を硬化させ、「契約違反で賠償請求するかもしれない」と脅すような言葉をかけてくるケースがあります。
ほとんどは心理的な圧力であり、実際に損害賠償が成立するケースはほとんどありません。
原則として、労働者が適切な手続きを踏んで退職すれば、会社が労働者に損害賠償を請求するのは困難です。
このような脅しを受けても、決して鵜呑みにせず、冷静に対応するようにしましょう。
SES退職によるトラブルの対処法

退職時にトラブルが発生すると、一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
しかし、対応が遅れるほど状況は悪化しやすく、退職のスケジュールや条件に影響が出る可能性があります。
ここでは、社内での相談から行政機関の活用まで、実際に取るべき行動を解説します。
より上の立場の上司や人事部に相談する
直属の上司との間で話し合いが行き詰まった場合は、さらに上の役職者や人事部に相談しましょう。
直属の上司は、現場の都合を優先して引き止めることがあります。
一方で、会社全体の立場から判断できる上司や人事担当者であれば、中立的かつ建設的な解決策を提示してくれる可能性が高いでしょう。
相談時は、就業規則や契約内容、メールやメッセージなどやり取りの記録を提示すると話がスムーズに進みます。
会社側も、一人の上司の不適切な対応が原因で法的な問題に発展する事態は避けたいはずです。
上層部や人事部が介入すれば、状況が改善されるケースは少なくありません。
管轄の労働基準監督署に通報・相談する

社内での解決が難しい場合や、明らかに違法な対応を受けている場合は、労働基準監督署への相談を検討しましょう。
労働基準監督署は、企業が労働基準法などの労働関係法令を遵守しているかを監督する厚生労働省の出先機関です。
未払い残業代や有給休暇の不当な拒否、不当な退職妨害など、労働基準法に関する違反を調査・是正する権限を持っています。
相談は無料で、匿名での情報提供も可能です。
申告を受けた労働基準監督署は、必要に応じて会社への立ち入り調査や、是正勧告を行います。
上司との会話の録音データや指示が書かれたメール、勤怠記録や就業規則のコピーなど、具体的な証拠を揃えて相談に臨みましょう。
話がスムーズに進み、より具体的なアドバイスや対応を受けられます。
SESの退職で損害賠償に発展する可能性があるケース

SES企業を退職する際、多くの場合は法的トラブルに発展せずに手続きを終えられます。
しかし、特定の行動をとると損害賠償請求を受けるリスクが高まることがあるため、注意が必要です。
こうしたケースを理解していないと、軽い気持ちでの行動が大きなトラブルを招きかねません。ここでは、実際に損害賠償に発展しやすい代表的な事例を紹介します。
事前相談なく無断で退職した場合
労働者には退職の自由が認められていますが、これはあくまで適切な手続きを踏んだ場合です。
就業規則や法律に従わず、突然出社をやめたり無断で辞めてしまったりすると、会社に損害が発生する可能性があります。
この場合、会社は業務の引継ぎがまったくできず、後任の手配もできません。
特にSESエンジニアの場合、常駐先に多大な迷惑がかかり、プロジェクトが停止するなどの実害が発生する可能性があります。
常駐先から自社に対して、契約不履行を理由に損害賠償や違約金を請求されることも考えられます。
どれほど会社に不満があっても、無断退職は避けましょう。
常駐先からの引き抜きで転職した場合

多くのSES企業では、入社時の誓約書や就業規則で在職中および退職後一定期間の引き抜き行為や、競合他社への転職を禁止する競業避止義務を定めています。
もしこれに違反して転職した場合、元のSES企業から違約金や損害賠償を請求されることがあります。
常駐先から魅力的なオファーがあっても、その場で安易に返事をするのは危険です。
まずは自社の就業規則を確認し、法的なリスクを慎重に検討する必要があります。
取引先に重大な損失を与えた場合
取引先に大きな損害が発生した場合も、損害賠償を求められる可能性があります。
これは退職そのものが原因ではありませんが、退職間際に意図的に会社や取引先に損害を与える行為をした場合です。
具体例としては、下記の行為が挙げられます。
- 機密情報の持ち出しや漏洩
- データの意図的な破壊
- 会社への誹謗中傷
これらは、単なる退職トラブルの域を超え、法的な責任を問われる重大な問題です。
退職時には感情的にならず、最後まで誠実な対応を心がけることが、自分自身を守ることにつながります。
SESの退職に適切なタイミングは?

退職の意思が固まったら、次はいつ伝えるか、タイミングを考えましょう。
退職の時期を誤るとプロジェクトや取引先に大きな迷惑をかけ、結果的に自分自身の評価を下げることにつながります。
SESの働き方は、自社だけでなく常駐先の業務進行や契約関係にも影響を与えるため、タイミングの見極めは特に重要です。
例えば、プロジェクトの節目や主要タスクが一段落した時期、または契約更新のタイミングが適切です。
これらの時期であれば、現場への影響を抑えられ、会社側も後任の任命や契約調整を行いやすくなります。
また少なくとも1~3ヶ月前には退職の意思を伝えることで、引継ぎや調整に十分な時間を確保でき、トラブルを回避しやすくなります。
こうした配慮を意識すれば、周囲との摩擦を減らし、円満退職につなげることが可能です。
円満退職後、前向きに働くには環境選びが重要です。
私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりが働きやすい環境を整えています。
案件選択制では、SESの経験を活かした案件やさらなる成長を見据えた案件を自由に選べます。
チーム制も採用しているため、たとえ未経験の分野でも経験豊富なベテランエンジニアのサポートを受けながら安心感を持って挑戦可能です。
また、高還元SESなど、エンジニアの希望やスキルに応じた柔軟な働き方ができます。
また会社間の単価をエンジニアに開示し、案件単価に応じた報酬が得られるため、納得感をもって働けるでしょう。
まずはお気軽に私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談を活用してみませんか?
今後のキャリア設計を一緒に考えましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
SESのプロジェクト途中で退職する場合の注意点

転職先の入社時期や自身のキャリアプラン、あるいは心身の健康状態によっては、プロジェクトの途中で退職せざるをえないでしょう。
プロジェクトの途中での退職自体は、法的に何ら問題ありません。
しかし、多くの関係者に影響が及ぶため、通常よりもさらに慎重な立ち回りが求められます。
ここでは、途中退職を円満に進めるための3つの重要な注意点を解説します。
退職の相談は1~3ヶ月前に行う
民法上は2週間前の申し出で退職可能ですが、プロジェクト途中の場合は、できる限り早く直属の上司に相談ベースで退職の意向を伝えることが大切です。
遅くても1ヶ月前、できれば2〜3ヶ月前には伝えておくと、退職がスムーズに進みやすくなります。
これは、後任者の選定や契約調整、取引先への説明などに十分な時間を確保できるようになるためです。
直前の相談はトラブルの原因になりやすいため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
双方の迷惑にならない期間を見計らう

退職時期を決める際は、自分の都合だけでなく、プロジェクトの進行状況や常駐先の繁忙期を考慮する必要があります。
大きなリリースや納期直前に退職すると、現場への影響が大きく、結果的に自分の評価を下げる可能性があります。
可能であれば、プロジェクトの区切りや一段落したタイミングを見計らうことで、双方にとって負担の少ない退職が実現できるでしょう。
退職までに必要な業務・手続きを明確にしておく
途中退職の場合は特に、後任への引継ぎが重要です。自分が抜けた後も、プロジェクトが滞りなく進むように、万全の準備を整える責任があります。
担当しているタスクの進捗状況や未完了の業務、使用しているツールや資料を整理し、後任者や関係者がスムーズに対応できるように準備しましょう。
また、備品返却や社内アカウントの処理など会社側の退職手続きも早めに確認し、計画的に進めることで余計なトラブルを避けられます。
特に、退職後も同じ業界で働く場合は、トラブルを抑えて退職することが双方にとってよいでしょう。
しかし、退職後のキャリアやプロジェクト調整について、不安を感じている方も少なくありません。
私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりが希望やスキルに合った働き方を実現できる環境を整えています。
案件選択制により、自身が思い描くキャリアや強みを活かした案件を自由に選べます。
未経験の分野でも、経験豊富なベテランエンジニアのサポートを受けながら安心感を持って挑戦可能です。
各案件のリーダーを狙え、開発フローの全体像を掴む道も進めます。
さらに、案件単価に応じた報酬が得られる単価給与連動制を導入しており、実力があるエンジニアほど高収入を得やすい仕組みです。
前職がうまくいかなくても、経験は無駄にはなりません。SESの経験を活かして、自分に合ったキャリアを実現しましょう。
少しでも興味のある方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
引き止められないスムーズなSES退職のポイント

SES企業を退職する際、辞めたいと伝えても思うように進まず、引き止められて交渉が長引くケースは少なくありません。
しかし事前に適切な準備をしておけば、引き止めをできる限り抑え、予定どおりに退職を進めることが可能です。
ここでは、スムーズな退職を実現するための具体的なポイントを解説します。
転職先から内定を獲得する
退職交渉を始める前に、次の転職先から正式な内定を獲得しておきましょう。
内定があることで将来の見通しが立ち、退職までの精神的な余裕が生まれます。
また、会社側に対しても退職の意思が一時的な感情ではなく、熟慮の末の決断であることを客観的に示せるはずです。
反対に内定がない状態で「辞めたい」と伝えてしまうと「不満があるなら改善するから」と交渉の余地を与えてしまい、話が長引く原因になります。
そのため、まずは転職活動を始め、内定をもらってから退職交渉に臨むことが効果的です。
さらに、内定を獲得するには、まず自分に合った企業を知ることが大切です。
その第一歩として、企業と直接話せる私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、入社後の働き方やキャリアイメージを事前に確認できます。
私たち高還元SES企業である私たちテクニケーションは、エンジニア一人ひとりが前向きに働ける環境を整えています。
高還元SESとは、エンジニアの単価に対する還元率が高いSES企業のことです。案件単価をエンジニアに開示しているため、納得のうえでキャリアを重ねることができます。
また案件選択制により、自身のキャリアや志向に合わせて案件を自由に選ぶことができます。資格取得を支援する制度もあり、学習しながら実務経験を積むことも可能です。
未経験の分野でも、チーム制により経験豊富なベテランエンジニアのサポートを受けながら安心感を持って挑戦できるでしょう。
SESエンジニアとしてキャリアアップを目指したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
退職理由を合理的に説明する

退職の意思を伝えると、まず聞かれるのが退職理由です。
この場面で感情に流されて、給与の低さや人間関係の不満などを率直にぶつけてしまうのは得策ではありません。
ネガティブな理由を前面に出すと、会社側は「改善するから残ってほしい」と説得材料にして引き止めてくる可能性が高いからです。
スムーズに退職するためには、会社が引き止めにくい合理的かつ前向きな理由を準備しておくことが重要です。
キャリアプランの実現や特定の事業領域への挑戦など、今の会社では実現できない理由を挙げると、説得力があります。
さらに、伝え方にも工夫が必要です。会社への不満を並べるのではなく、前向きな表現を添えることで、角が立ちにくくなります。
合理的で前向きな理由を冷静に伝えることができれば、会社側も受け止めやすく、引き止めが長引く可能性を減らせます。
引継ぎを確実に行う
退職をスムーズに進めるうえで、引継ぎは重大なポイントです。
自分が担当してきた業務を後任者がスムーズに引継げるよう準備しておくことで、現場や会社への負担をできる限り抑えられます。
具体的には日々の業務手順や注意点、利用しているツールの使い方、取引先や関係者との連絡体制などをドキュメント化して整理しておきましょう。
口頭での説明だけでは抜け漏れが発生しやすいため、チェックリストやマニュアルとして残すことが大切です。
さらに、後任者が業務に慣れるまでに必要な期間を見積もり、引継ぎのスケジュールを立てて進めることも有効です。
また、引継ぎの進捗は定期的に上司へ報告しましょう。
もし引継ぎを疎かにしてしまうと、引き止めの口実を与えたり、退職後に問い合わせの連絡が来たりする原因になります。
円満退職を実現するためにも、後任がすぐに業務を続けられる状態を整えることを意識して引継ぎに取り組みましょう。
期日までに各種手続きを完了させる

退職時には、下記のようなさまざまな事務手続きが発生します。
- 健康保険証の返却
- 社員証や貸与パソコンの返却
- 会社指定の書類提出
これらの手続きを、定められた期日までに漏れなく完了させることも、スムーズな退職の重要なポイントです。
書類や手続きが滞ると退職が延びてしまう原因になります。
退職日が近づくと、引継ぎや有給消化で忙しくなりがちですが、やらなければならない各種手続きをリストアップして一つひとつ丁寧にこなしていきましょう。
退職まで社会人としての基本をきっちり守る姿勢が、円満な退社につながります。
SES退職後のキャリアの選択肢

SESを退職した後のキャリアには、複数の道があります。自分のスキルや志向性に合わせて比較検討すれば、後悔のない選択ができるでしょう。
まずは、別のSES企業への転職です。常駐先の種類や案件の幅は企業ごとに異なるため、より希望に合った環境を選ぶことができます。
特に高還元SES企業であれば、単価開示や給与還元率の高さが明確で、納得感を持ちながら働けるのが大きな特徴です。
次に、自社開発企業の選択肢もあります。自社サービスの企画から運用まで携われるため、長期的にプロダクトに関わりたい方に向いています。
人気が高いため、実務経験やスキルのアピールが重要です。
また、SIer(システムインテグレーター)への転職も選択肢のひとつです。
要件定義や設計など上流工程に関わることが多く、マネジメントスキルを高めたい方に適しています。
SES退職後のキャリアを考える際は、自分が何を優先するかを軸に選ぶことが重要です。
収入・技術力・働き方の自由度など、一人ひとり重要視するポイントは異なります。
私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりが理想のキャリアを築けるよう、高還元SESや案件選択制などの仕組みを整えています。
単価をエンジニアに開示する透明性や、チームで連携して働ける体制など、キャリア形成に有益な環境が整っているのが強みです。
経験豊富なベテランエンジニアのサポートを受けられるため、未経験の分野に挑戦しやすいのも魅力です。
これまでのSESの経験を活かすのも、新しい分野に挑戦するのも自由に選択できるため、モチベーション高く働けます。
自分に合ったキャリアを私たちテクニケーションで一緒に見つけませんか?まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談でお気軽にお話ししましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
SESを円満に退職して新しいキャリアに向けて踏み出すなら

SESを退職した後「次はどのような職場を選べば安定したキャリアを築けるのか」と不安を抱える方は少なくありません。
大切なのは、スキルを正しく評価され、納得感を持って働ける環境を選ぶことです。
私たちテクニケーションは、そのための仕組みを整えています。
単価給与連動制では、案件単価に応じた報酬が得られるため、モチベーションを高く維持できます。
さらに、案件選択制を導入しているため、自分のキャリアプランや得意分野に合った案件を主体的に選ぶことが可能です。
加えて、チーム制によっていつも仲間と連携しながらプロジェクトを進められるため、一人で孤独に働く不安も軽減されます。
このような環境は、円満退職後に不安を軽減しながら次のキャリアをスタートさせるために必要不可欠です。
私たちテクニケーションでは、気軽に参加できる専門アドバイザーによる無料相談を実施しており、制度や働き方を直接質問できます。
SESエンジニアとして新しいキャリアを目指したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。
新しいキャリアの可能性についてご相談いただけますと幸いです。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!





















