サーバーエンジニアに必要な勉強は?必要スキルやおすすめの資格、勉強方法を解説

サーバーエンジニアとして日々の業務に向き合うなかで、このままでよいのか、何を学べばキャリアが開けるのか将来に漠然とした不安を抱いていませんか?
技術の進化が速いIT業界では、数年前まで主流だったスキルが、あっという間に古くなってしまうことも珍しくありません。
SESの働き方では、案件に追われて自分の成長戦略を立てる余裕がない方も少なくないでしょう。
本記事ではサーバーエンジニアとして働くあなたがこれからの変化に対応し、自らの市場価値を高めるために必要なスキルや資格、勉強方法を実務目線で解説します。
自分の学びがどのような案件や業務に結びつくか、今後のキャリアをどのように築いていくか、その道筋が明確に見えてくるはずです。
目次
サーバーエンジニアの仕事内容

サーバーエンジニアは、企業や組織のITインフラを支える重要な職種です。
しかし設計や構築、保守と運用などの言葉が並ぶものの、それぞれの業務内容や必要なスキルの把握は難しいと感じる方も少なくありません。
以下では、サーバーエンジニアの具体的な業務とその役割を解説します。
サーバー設計
サーバー設計は、システムの安定稼働を支える基盤作りの第一歩です。
利用者数や用途、必要なスペックなどに基づいて、適切な構成を練り上げていきます。主な業務には以下が含まれます。
- 要件定義に基づいた構成案の策定
- サーバースペックや台数の選定
- セキュリティ要件の盛り込み
- 拡張性や可用性の設計
設計段階での判断がシステムの信頼性や運用コストに大きく影響するため、論理的思考力やIT全体の知識が問われるフェーズです。
サーバー構築

設計された構成をもとに、実際にサーバー環境を構築するフェーズです。
物理サーバーの組み立てから仮想環境の設定まで、技術力が必要とされます。構築作業では以下の工程が行われます。
- OSのインストールと初期設定
- ネットワーク設定やDNS構成
- サービス(WebサーバーやDBなど)の導入と設定
- セキュリティ設定(ファイアウォールやアクセス制御)
この工程では正確な手順理解とトラブル時の対応力が重要です。特にクラウド環境での構築経験は、今後ますます重視されます。
サーバーの保守や運用
保守や運用業務では、構築後のサーバーが安定して稼働し続けるように、日々の監視やメンテナンスを行います。
代表的な業務は以下のとおりです。
- 稼働監視ツールによる状態チェック
- 障害対応(ログ確認、リカバリ作業など)
- パッチ適用やアップデート
- 利用状況のレポート作成
トラブル発生時の初動判断や改善提案力が求められるため、経験を積むほど対応力に差が出やすい領域です。
サーバーエンジニアの将来性やキャリアパス

IT業界の技術革新は止まることなく進み続けています。そのなかでも、サーバーエンジニアはインフラの根幹を支える存在です。
現代はクラウドの普及が加速し、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド環境の設計や運用をできるスキルも求められます。
さらに、システムの信頼性を担保する設計段階からのセキュリティ対策、構成管理の自動化に対応できる柔軟性が重視されるようになりました。
そのためサーバーエンジニアは今後も高いニーズが期待される職種で、将来的なキャリアの選択肢も豊富です。
インフラ領域の技術を深めていけば、クラウドエンジニアやSRE(Site Reliability Engineer)、インフラアーキテクトなどの専門性の高いポジションを目指すことができます。
一方で、現場での経験を活かしてプロジェクト全体を統括するマネージャーやリーダーとしてステップアップする道も開かれています。
技術志向かマネジメント志向か、志向性に応じた柔軟なキャリア形成が可能です。
キャリアを具体的に描くには、自分の現在地を把握し成長に必要な知識や経験を明確にしておくことが大切です。
クラウド系の資格取得を通じて新しい技術を習得したり、プロジェクトの進行管理に関わってみたりと、意図的にチャレンジの場を選ぶことが将来への一歩につながります。
私たちテクニケーションでは、あなたのキャリア志向や習得したい技術に応じて案件を自由に選べる案件選択制を採用しています。
たとえば、クラウド移行プロジェクトやSREチームへの参画など、これまで経験のなかった分野にも積極的にチャレンジすることが可能です。
さらにチーム制を導入しているため、わからないことがあってもベテランエンジニアからのサポートを受けられ、安心して業務に取り組むことができます。
また、会社間の単価をエンジニアに開示しており、報酬の還元率が高く案件単価に応じて報酬がアップする単価給与連動制を採用しているため、納得感と成長実感の両立が可能です。
新しい技術に挑戦したい方、将来のキャリアを見据えて一歩踏み出したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、自身の理想のキャリアをお聞かせください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
サーバーエンジニアになるには

サーバーエンジニアを目指すうえで大切なのは、何を学ぶかだけではなく、どのような順序でステップを踏むかです。
単に資格を取るだけでは実務で即戦力になるのは難しく、現場で求められる技術や姿勢を理解したうえでの準備が求められます。
まずは、サーバーの仕組みや基本的な構成の理解が必要です。OSやネットワーク、セキュリティなどの基礎技術の知識は、日々の業務の土台になります。早い段階で身につけておくとその後の学習がスムーズです。
特にLinuxは現場でよく使われており、実際にコマンドを使いながら覚えると理解も深まります。そのうえで、仮想環境やクラウドサービスを使った構築経験を積むことが、実務に直結するスキルを養ううえで効果的です。
仮想マシンを使えば、実際にサーバーの立ち上げから設定までを手元で何度でも試せるため、失敗を恐れずに実践できます。
実践経験は、履歴書に記載する資格よりも説得力を持つこともあります。また、サーバーエンジニアの業務は単独では完結せず、他チームや利用者との連携が必要です。
技術力とあわせて柔軟なコミュニケーション力や対応力も評価される要素です。状況を読み取って、適切な判断ができることがプロフェッショナルとしての価値につながります。
サーバーエンジニアに必要な勉強

サーバーエンジニアとして活躍するためには、日々の業務経験だけでなく、確かな知識の積み重ねが欠かせません。
安定したキャリアを築くためには、基礎から応用まで幅広い分野の理解が必要です。
本記事では、サーバーエンジニアを目指す方・すでに現場で活躍している方に向けて、押さえておきたい基礎知識や実務で役立つ技術分野をわかりやすく解説します。
知識を体系的に整理し、自信を持って現場に臨むための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
IT基礎知識
IT業界で土台となるのがIT基礎知識です。特に以下の概念はサーバーエンジニアにとって必須です。
- コンピューターの仕組み
- ファイルシステムの概念
- ソフトウェアとハードウェアの関係
- バッチ処理やプロセス管理の考え方
ITパスポートや基本情報技術者試験などの内容に触れることで、基礎を体系的に理解できます。
サーバーの仕組み
サーバーの仕組みの理解は、エンジニアとしての第一歩です。具体的例は以下のとおりです。
- クライアントとサーバーの関係性
- Webサーバーやファイルサーバーの役割
- サーバー間通信の流れ
サーバーがネットワークのなかでどのように機能しているのかをつかむ必要があります。
OSの知識
サーバーのOSは、Windows ServerやLinuxが中心です。それぞれの基本操作に加えて、以下のコマンド操作も重要です。
- ファイルやディレクトリの管理
- パーミッション設定
- サービスの起動や停止
- シェル操作やスクリプト
特にLinuxは、コマンドベースでの操作に慣れておくことが構築や保守に役立ちます。
ネットワークの知識

サーバーはネットワークに接続して初めて価値を発揮します。そのため、以下の基本的なネットワーク知識は不可欠です。
- IPアドレスとサブネットマスク
- ルーティングの概念
- DNSやDHCPの仕組み
- ポートとプロトコルの役割
これらを理解できれば、通信エラーの原因特定や設定時のトラブル防止に役立ちます。
セキュリティの知識
サーバーは常に外部からの脅威にさらされています。以下のセキュリティ知識を持つことは、企業の信頼性を守るうえでも重要です。
- ファイアウォールの設定
- アクセス権の設計
- ログ管理による監視
- 脆弱性への対応
守る力はエンジニアの価値を高める要素として注目されており、学習しておくことで提案力にもつながります。
クラウドの知識

現在のサーバー環境はクラウドとの共存が前提です。AWSやAzureなどの主要クラウドサービスに触れ、以下のようなポイントを学びましょう。
- 仮想サーバーの立ち上げ
- ストレージとネットワークの構成
- サーバーレス構成の理解
- 自動化ツール(TerraformやAnsible)との連携
クラウド技術はサーバーエンジニアのキャリアを広げる武器になります。そして、実際に学び得た知識をどのように現場で活かすかが次のステップです。
私たちテクニケーションでは、資格取得支援制度を設け、会社全体でエンジニアのスキルアップを後押ししています。
また、チーム制も採用しているため、ベテランエンジニアとともに業務に取り組むことができ、安心してチャレンジできる環境が整っています。
これにより、これまで挑戦できなかった案件にも安心感を持って取り組むことができ、習得した知識をすぐにアウトプットすることが可能です。
特に成長フェーズにあるエンジニアにとっては、自身の努力がダイレクトに評価される環境は、大きなモチベーションになるはずです。
まずは、自身がどのようなキャリアを描いているのか、どのような知識を身につけたいのか、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談でお聞かせください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
サーバーエンジニアに必要なスキル

サーバーエンジニアとして活躍するためには、単に機器を扱えるだけでは不十分です。
インフラの安定運用や効率的な構築・運用を支えるためには、実務に活かせるスキルを身につけ、課題に柔軟に対応できる技術力が求められます。
現場で信頼されるエンジニアになるためには、どのようなスキルを身につけるべきなのかを理解しておくことが重要です。
以下では、現場で求められるサーバーエンジニアの代表的なスキルをピックアップし、それぞれの重要性と活用場面を具体的に解説します。
サーバー構築スキル
サーバー構築は、サーバーエンジニアの中核を成すスキルです。具体的には以下のような作業が含まれます。
- OSのインストールと初期設定
- サービスの導入と構成
- ネットワーク設定と接続確認
- クラウド環境でのインスタンス作成
これらはインフラの土台を作る工程であり、業務の信頼性に直結するスキルです。
基本設計スキル

要件を満たし、なおかつ効率的で将来的な拡張性にも対応できる設計を行う必要があります。以下は、構築の前段階として重要な基本設計スキルです。
- システム要件からサーバー構成を導き出す力
- ネットワークやセキュリティの設計
- 可用性や冗長性の考慮
- ドキュメント化による情報共有
設計力はキャリアの上流工程へ進むうえで欠かせないスキルです。
プログラミングスキル
サーバーエンジニアにも、一定のプログラミングスキルが求められるようになってきています。特に以下のような用途で使用されます。
- シェルスクリプトやPowerShellによる自動化
- Pythonなどによる監視スクリプトの作成
- インフラ構成管理ツールとの連携(Terraform、Ansibleなど)
コードを書けるインフラエンジニアはDevOpsのような役割も担え、キャリアの幅を広げることが可能です。
トラブルシューティング・問題解決スキル

どれだけ正確に構築してもトラブルは発生するため、求められるのが以下のような迅速かつ的確な対応力です。
- ログやモニタリングツールを使った原因調査
- 仮説立てと検証による問題解決
- 再発防止策の実装と報告
トラブル対応の経験が豊富なエンジニアは現場で重宝されます。
しかしいくらスキルを習得しても、現場で経験へと昇華できなければ意味がありません。
私たちテクニケーションでは、スキルや資格の取得を会社全体でサポートしています。
資格取得支援制度やチーム制の導入で、新しい領域への挑戦を学習面や精神面でもしっかりと支えることができます。
経験豊富なベテランエンジニアからの技術サポートやフィードバックが日常的に得られ、実務を通じて着実な成長が可能です。
また、案件選択制により構築や設計、トラブル対応など自分が強化したいスキルにフォーカスした案件に挑戦できます。
さらに会社間の単価をエンジニアに開示する仕組みにより、納得感を持って働くことができます。
サーバーエンジニアとして、私たちテクニケーションで一緒にキャリアアップしてみませんか?まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、自身の理想のキャリアをお気軽にお話ください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
サーバーエンジニアにおすすめの資格

サーバーエンジニアとしてスキルを証明するうえで、資格の取得はとても有効です。
第三者からの評価を得られるスキルを示すことができるのは、資格ならではの強みです。
この章では、サーバーエンジニアがキャリアアップを目指すうえで取得しておきたい代表的な資格を3つ紹介します。
LinuC
LinuC(リナック)は、LPI-Japanが提供する日本国内向けのLinux技術者認定資格です。
以下のLevel1〜3まであり、各レベルで以下のスキルを証明できます。
- Level1:基本操作やユーザー管理、パッケージ管理など
- Level2:ネットワーク設定、セキュリティ、サーバー構築など
- Level3:クラスタリング、高可用性、仮想化など
Linuxを扱うサーバーエンジニアにとって、基礎〜応用を網羅できる認定資格として信頼性が高いです。
LPIC
LPIC(エルピック)は、LPI(Linux Professional Institute)が提供する、グローバルで通用するLinux技術者向けの認定資格です。
Level1からLevel3までの段階があり、それぞれのレベルで実務に直結するLinuxのスキルが求められます。
ベンダーに依存しない中立的な立場で設計されているため、Red HatやUbuntuなど、特定のディストリビューションに偏らず幅広く対応できる知識が身につきます。
特に海外企業とのプロジェクトに携わる機会がある方や、外資系企業への転職を視野に入れている方にとっては、国際的な評価の高いLPICは強いアピール材料です。
マイクロソフト認定資格(Windows Server系)
Windows Serverを扱う現場では、マイクロソフト認定資格(旧MCP、現在はMicrosoft Certified)が有効です。代表的なものは以下が挙げられます。
- Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
- Microsoft Certified:Windows Server Hybrid Administrator Associate
これらの資格では、オンプレとクラウドをまたぐ実務スキルの証明が可能です。クラウド活用が前提となる今、とてもニーズが高まっている資格です。
サーバーエンジニアの勉強におすすめの書籍
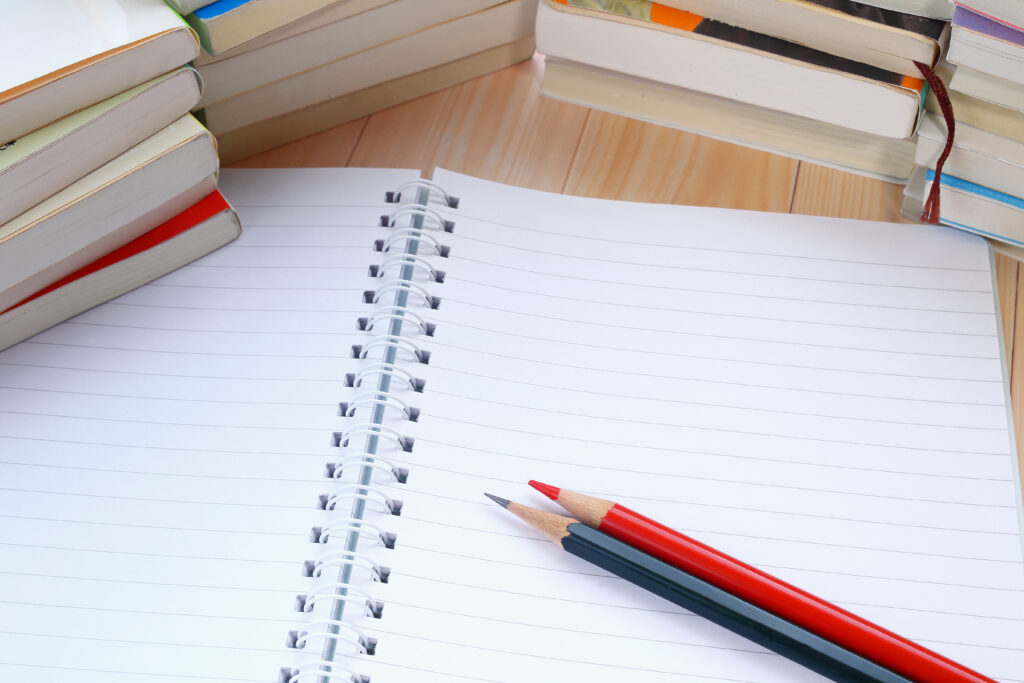
サーバーエンジニアの勉強には動画やWebサイトだと断片的になりやすいため、全体像を体系的に学べる書籍は、基礎の定着や復習にも適しています。
Linuxの基礎を学ぶなら『Linux標準教科書』(LPI-Japan発行)が入門書としておすすめです。
LinuCの公式教材であり、コマンド操作やファイル構成、ネットワーク設定などの基本を実習形式で学べるよう設計されています。
構築スキルを一から学びたい場合には『できるPROシリーズ サーバー構築入門』が役に立ちます。
CentOSやWindows Serverを用いた構築手順が丁寧に解説されており、実務に近い環境を再現しながら理解できる内容です。
クラウド分野に関心がある方には『AWS認定資格試験テキスト AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト』をおすすめします。
試験対策用でありながら、実務に直結するサービス選定や設計方針も解説されています。
また、より全体像をつかみたい方には『AWS認定クラウドプラクティショナー』向けテキストもおすすめです。
基礎レベルから幅広くサービスを学べる内容になっており、初心者のクラウド入門に適切です。
それぞれの書籍には明確な特徴があり、自分の現在のスキルレベルや目標と照らしあわせて選び、無駄なく学習を進めましょう。
サーバーエンジニアの効率のよい勉強方法

日々忙しいなかでスキルアップを目指すサーバーエンジニアにとって、限られた時間をいかに効率よく活用するかは大きな課題です。
この章では、サーバーエンジニアが短時間でも実践的な学習を積める効率的な勉強方法を紹介します。
現場で即戦力となるスキルを身につけたい方にとって、有用な手段が見つかるはずです。
Webサイトで勉強する
スキマ時間を活用できる手段として、有益な学習サイトの活用があります。代表的なものとして以下が挙げられます。
- QiitaやZennでの実例学習
- LinuC公式サイトの模擬問題や解説ページ
- Progateやドットインストールでの基礎固め
特にQiitaやZennでは現場の課題とその解決法が共有されており、実践的な知識が身につきやすいのが魅力です。
仮想マシンを使って実践的に学習する
実機を用意しなくても、自宅のPCに仮想マシン(VirtualBoxやVMware)を構築すれば、サーバー環境を手軽にシミュレーションできます。
仮想環境のメリットは、OSのインストールから設定まで一連の操作を反復練習できる点や実務で使われるUbuntuやCentOSなどLinuxを自由に選んで試せる点などが挙げられます。
また、トラブルが発生してもすぐにリカバリできるため、失敗を恐れずに挑戦できる環境です。
理論だけでなく、自分の手を動かして試行錯誤を重ねることがサーバーエンジニアとしての確かな実力を養ううえで重要です。
専門スクールやオンラインコースに通う

自学に限界を感じる場合は専門スクールやオンライン講座の活用も考えましょう。以下のような講座が注目を集めています。
- Udemyのインフラ講座(AWS、Linux、ネットワークなど)
- TechAcademyやRaiseTechなどの実務直結型講座
- LinuC試験対策に特化したオンラインスクール
講師からのフィードバックが得られるため、自己流の学習で気付けなかった理解の抜けや癖修正ができます。
効率よく学ぶためには、自分のライフスタイルや習熟度に合った方法を選ぶことがとても重要です。
無理なく、かつ着実にステップアップできる方法の選択で、勉強の継続性と成果が大きく変わります。
私たちテクニケーションでは、学習意欲のあるエンジニアが力を発揮できる制度を採用しています。
学習面では資格取得支援制度を採用しスキルアップを積極的にサポートしています。
また、習得した技術や知識に応じて適切な案件を自分で選択できる、案件選択制度も導入しています。
さらに、チーム制により経験豊富なベテランエンジニアによるフォローも受けられるため、学習直後でも安心感を持ってチャレンジできる環境です。
勉強だけで終わらせたくない、次のフェーズに進みたいとお考えの方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で理想のキャリアをお聞かせください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
サーバーエンジニアの勉強は独学でもできる?

サーバーエンジニアとして必要な勉強は独学でもできるのかは、エンジニアが抱える共通の悩みです。
以下では独学とスクールの違い、それぞれのメリットやデメリットを整理しながら、自分に合った学習スタイルを選ぶための判断材料を提供します。
独学の魅力は、コストを抑えつつ自分のペースで学習できることです。特に以下のようなメリットがあります。
- 学習時間を自由にコントロールできる
- 実務と並行しながら学べる
- 書籍やWeb教材を自分の興味に応じて選べる
一方で理解が曖昧なまま進んでしまう、学習が断続的になる、モチベーションが維持しにくいなどの課題もあります。
そのため独学を成功させるには、学習計画を明確に立て、定期的にアウトプットしたり模擬試験や仮想環境での実践を取り入れたりする工夫が欠かせません。
スクールを利用する場合、費用はかかりますが次のようなメリットがあります。
- カリキュラムに沿って段階的に学べる
- 講師からフィードバックを受けられる
- 実務に近い演習が豊富
- 学習コミュニティによるモチベーション維持
特に時間の確保が難しい社会人にとっては、短期間で効率よくスキルを習得するための手段として有効です。
どちらがよいかは一概にはいえませんが、自己管理能力が高く、すでにある程度のITリテラシーがある方は独学でもできます。
一方で、ゼロからのスタートやしっかりとスキルアップを図りたい方には、スクールの利用がおすすめです。
必要なスキルや資格を勉強してサーバーエンジニアにキャリアチェンジするなら

今の仕事に将来性を感じられず、これからの働き方を変えたい、一生モノのスキルを身につけたいと感じる方にとってサーバーエンジニアはとても魅力的な選択肢です。
しかし、キャリアチェンジを目指すにあたっては、単に学習を始めるだけでは不十分です。
どのようなスキルを、どのような環境で身につけるかが、その後のキャリアを大きく左右します。
成長したい気持ちはあっても現場で学べる内容が限定されてしまい、参画する案件を自由に選べない環境では、自分が望む方向に進むことが難しくなってしまいます。
私たちテクニケーションの環境は、キャリアチェンジを目指す方にとって、とても心強い味方です。
案件選択制を採用しているため、自分のスキルや興味に合ったプロジェクトを主体的に選ぶことができ、納得感を持ちながら成長が可能です。
経験の浅いフェーズでも、チーム制によってベテランエンジニアの支援を受けながら現場に入れるため、安心感を持って業務に取り組める環境が整っています。
資格取得支援制度も充実しており、勉強しながら実務経験を積むなどのキャリアチェンジに適切な仕組みが構築されています。
これまでの経験を活かしながら、新たな分野で自分らしいキャリアを築きたいとお考えなら、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談をご活用ください。
自分では気づけなかった可能性や、今後のキャリアの方向性がきっと見えてくるはずです。
私たちと一緒に、サーバーエンジニアとして理想のキャリアを築いていきましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!





















