フルスタックエンジニアはいらないといわれる理由は?需要がある理由や活躍するためのスキルを解説

フルスタックエンジニアという言葉を聞くと、幅広く対応できる万能型のエンジニアというイメージが浮かぶ一方で、いらないのではといった声も耳にします。
SESで働く立場からすると、どこまで追求するべきか迷う方も少なくないでしょう。
実際、浅く広い知識は中途半端にみられることもあり、専門性を求める現場では評価されにくい傾向です。
しかし同時に、少人数チームやクラウド環境が主流となった今では、幅広い知識を持つ人材が重宝されるケースも増えています。
本記事では、フルスタックエンジニアの定義といらないと言われる理由や、需要が高まっている背景を整理しながら、キャリアにどう活かせるのかを解説します。
読み終えたときには、自分の強みをどのような環境で活かせるかが見えてくるでしょう。
目次
フルスタックエンジニアとは

フルスタックエンジニアとは、フロントエンドやバックエンド、クラウド環境まで一通り対応できるエンジニアを指します。
複数の言語を扱えるだけでなく、開発の流れを俯瞰して理解し、幅広い領域をつなげられる点がフルスタックエンジニアの強みです。
SESの現場でも、小規模チームで幅広い業務を任される案件において、その力を発揮します。
また、専門特化のエンジニアが集まる大規模チームでも、フルスタック人材が加わることで全体の進行がスムーズになり、課題解決の幅も広がります。
フルスタックエンジニアの仕事内容

フルスタックエンジニアは、開発の全工程に関わることが多く、担当範囲は幅広いです。
フロントエンドでは機能開発を行い、バックエンドではサーバーサイドの処理やデータベース設計などを担当し、Java・Python・Node.jsなどが用いられます。
さらにサーバーやクラウド環境の構築も求められ、AWSやGCPを用いたインフラ設定、セキュリティ対策、運用自動化も含まれます。
そして運用・保守フェーズは障害対応やログ監視、パフォーマンス改善を行い、システムの安定稼働を支えている工程です。
この仕事内容を把握することで、自分が経験している領域や不足している分野を整理でき、次に伸ばすべきスキルや案件選びの判断材料になります。
フロントエンド開発業務
フロントエンド開発は、ユーザーが実際に目にして操作する画面や機能を形成する工程です。
具体的にはHTMLやCSS、JavaScriptといった言語を用いて、見た目や操作性を設計・実装します。
さらに、公共機関が提供するWebサイト構築では単に見た目を整える以上に、セキュリティやアクセシビリティといった要件を満たすことが求められます。
多様な立場の利用者が使いやすい設計の両立が重要視されている点も注目です。
バックエンド開発業務

バックエンド開発とは、目に見えない裏側でシステムを支える重要な役割です。
まず、エンジニアはシステムの要件を整理し、全体の構造や利用するプログラミング言語を決定します。
その後、ユーザーの操作やリクエストに基づいて動くプログラムやデータベースを設計・構築し、適切に処理と保存が行われる仕組みを作ります。
システムが公開された後は保守・運用にも関わり、問題が生じた際の障害対応やパフォーマンスの改善を通じて、サービスが継続して安定稼働するよう支える工程です。
サーバー・インフラ構築業務
サーバー・インフラ構築業務では、システムを支える土台作りが主な役割です。
近年は、コードでインフラを管理することが重視されており、環境の再現性・自動化が進んでいます。
医療分野など特定の業界では仮想サーバー環境の設計から設定・試験・接続調整、さらには保守まで一貫して担当するケースもあり、構築の幅広さが求められます。
システム運用・保守業務
システム運用・保守の主な目的は、システムを安定して稼働させるだけでなく利用者へのサービスを継続的に改善し、運用コストを削減することです。
そのため、担当者はインシデント対応や障害時の復旧・定期点検・バックアップ体制の確保・パッチの適用といった幅広い業務に取り組みます。
実際には、利用者や関係者への連絡・原因調査・報告書作成といったプロセスも含め業務全体を見通せる対応力が求められます。
フルスタックエンジニアがいらないといわれる理由

フルスタックエンジニアは幅広い領域を扱える強みを持つ一方で、器用貧乏とみなされることがあるのも事実です。
これは、多数の技術に触れる分だけ、特定の分野で深い専門性を発揮しにくいと考えられるためです。
また、プロジェクトによっては役割分担が明確に決まっており.フロントエンド・バックエンド・インフラの専門エンジニアがそれぞれ配置されています。
そのため、フルスタックエンジニアである必要性が薄れる場合もあります。
さらに、自己紹介やスキルシートでフルスタックエンジニアと表現しても具体的にどの領域をどの程度扱えるのかが相手に伝わりにくく、評価が曖昧になってしまうこともあるでしょう。
誤解と実態を切り分けて理解することが、自分のキャリアを考えるうえで重要です。
器用貧乏でスキルレベルが低いと思われがち
フルスタックエンジニアが器用貧乏と言われるのは幅広い技術を扱える反面、各分野で深い専門性を持っていないようにみられることが理由です。
また、自己紹介やスキルシートで幅広く対応できると伝えると、何でもできるけど特に何かに秀でているわけではないという受け止められ方をされてしまい、評価が曖昧になりやすいのも現実です。
こうした誤解に対して、読み手が明確に理解できるように自分の強みや得意領域を文章で具体的に表現し、補足する姿勢が重要といえます。
得意分野がわかりにくい

フルスタックエンジニアは何でもできるという強みを持っている一方で、特に何が得意なのかが相手に伝わりにくいという課題があります。
得意分野が曖昧だと、採用や評価の場面で役割がぼやけていると見なされ、結果として評価が不明瞭になりやすいのです。
このような受け止められ方を避けるには、自分の得意領域を具体的に示し、深さと幅の両面でアピールする表現を工夫することが大切です。
フルスタックエンジニアが必要ないプロジェクトもある
すべてを自分一人でこなせるフルスタックエンジニアは魅力的ですが、プロジェクトの性質によってはかえって必要とされないこともあります。
特に大規模な現場や高度な専門性を求められる案件ではフロントエンド、UXなどが明確に分かれており、それぞれに特化したエンジニアが配置されています。
それにより、幅広いスキルを持っていても活かしにくい構造です。
そのため、プロジェクトの規模やチーム構成、必要とされる専門性に応じて全体型より特化型の方が望ましいケースもあるでしょう。
実際にはフルスタックエンジニアの需要がある理由

フルスタックエンジニアはいらないという声がある一方で、現場では依然として高い需要があります。その理由の一つが、開発スピードの向上です。
フロントからバック、インフラまで一人で対応できれば部門間の調整に時間を割かずに進められ、特に小規模チームやスタートアップで効果を発揮します。
また、人件費削減の観点でも価値があります。専門エンジニアを複数人揃えるより、幅広く対応できる人材を配置した方がコストを抑えられるため、SES企業や受託案件では重宝される傾向です。
さらに、幅広い知識を持つことで設計やレビューにも貢献でき、チーム全体の品質向上にもつながります。
こうした背景から、プロジェクト規模や業種によっては専門職よりも高い柔軟性と価値を提供できるため、市場での必要性は存在しています。
開発スピードが速くなる
フルスタックエンジニアは幅広く対応できるため、複数工程でエンジニア同士の連携を待つ必要がなく、開発全体をスムーズに進められます。
全体を見渡して動ける点は、開発の効率と柔軟性を大きく高める強みです。
スピード感ある環境で成長したい方には、私たちテクニケーションが提供するチーム制の案件が適しています。
ベテランエンジニアからのサポートを受けながら業務に臨めるだけでなく、開発フロー全体を学びつつ各案件でリーダーを目指すチャンスもあります。
さらに、幅広い工程を経験することで自分の強みや得意分野を明確にでき、将来のキャリア選択や年収アップにもつなげられることも魅力の一つです。
SESの現場で実践的なスキルを積み、市場価値を高めたい方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談を活用ください。
私たちとともに理想の働き方を目指しませんか?
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
人件費削減につながる

フルスタックエンジニアは幅広く対応できるため、複数の専門エンジニアを揃えるよりも効率的でコストを抑えられるのが大きなメリットです。
特にスタートアップや小規模プロジェクトにおいては、一人のフルスタックが一元的に対応する方が、コスト削減になることもあります。
限られた予算で成果を求められる現場では、フルスタック人材がとても重宝されています。
幅広い知識によるプロジェクト貢献が期待できる
フルスタックエンジニアは複数の技術を横断的に理解しているため、開発の各工程で発生する問題や仕様変更にも即座に対応できる力を持っています。
多岐にわたる知識を武器にプロジェクトを効率的かつ柔軟に前進させる存在は、チーム内で頼りにされるでしょう。
新しい環境でスキルを磨きたい方には、私たちテクニケーションのチーム制案件がおすすめです。
ベテランエンジニアからの丁寧なサポートを受けながら、挑戦と成長を重ねられる環境が整っています。
さらに、開発フロー全体を理解しつつ各案件でリーダーを任される機会もあり、フルスタックエンジニアとして幅広い知識を活かした実践的な経験を積むことができます。
こうした経験は市場価値を高め、将来のキャリアアップにもつながります。次のステップを考えている方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談を活用してください。
自分に合った案件を一緒に見つけ、理想のキャリア形成の第一歩を踏み出しましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
フルスタックエンジニアが活躍しやすい職場

フルスタックエンジニアは、一人で幅広い工程を担えるため、特定の環境では大きな力を発揮します。
例えばスタートアップでは、限られた人員でプロダクトを素早く作る必要があり、設計から実装、運用までを横断できる人材は重宝されます。
中小企業では、専任担当が不足しがちなため、幅広い知識を持つエンジニアが全体のバランスを取りながら開発を前進させられるでしょう。
そしてSES企業では、多様な案件に携われる点が強みとなり、経験の幅を広げながら専門性を深めるチャンスにつながります。
キャリアを考えるうえで、どのような環境なら力を発揮できるのかを意識することが、より満足度の高い働き方につながるでしょう。
スタートアップ企業
スタートアップ企業は、少数精鋭のチームでスピーディにプロダクトを立ち上げる必要があるため、フロントエンドからインフラまで幅広く担当できるフルスタックエンジニアが活躍しやすい環境です。
初期段階では人員や予算に限りがあるなかで、一人が複数の工程を担えることは、開発の迅速化やコスト削減に直結します。
またスタートアップで活躍できるメリットとしては、不足する工程を自分の手で補える現場力などが挙げられ、学習速度と成長の加速にもつながります。
IT化を推進したい中小企業

中小企業、特にIT化やDXを推進したい企業では専門エンジニアを複数人採用する余裕がないケースが多数です。
そのような環境では、幅広い領域に対応できるフルスタックエンジニアは特に重宝される存在といえます。
業務システムの導入・既存サイトの改善・顧客対応の仕組み構築など、多様な業務を一人で対応できることは、コストも手間も抑えつつ効率的なIT推進につながります。
フルスタックエンジニアは、マルチな対応力を活かして即戦力として活躍できる希少な人材となるでしょう。
SES企業
SES企業では、幅広いスキルを持つフルスタックエンジニアが多様な案件に参加できる仕組みが整っている場合、価値がより一層高まります。
開発の幅広さを武器に、フルスタックエンジニアとして自身の強みを活かせます。スキルチェンジや成長意欲を持つエンジニアにとっては、自分らしく働きながら評価される場となるでしょう。
そのような制度が整った環境でさらに前進したい方には、私たちテクニケーションのSES案件マッチングがおすすめです。
単価給与連動制により、案件単価に応じて報酬が反映されるため、公正な評価を実感しやすい仕組みが整っています。
また案件選択制によって、キャリア目標や興味に合わせた案件を自由に選ぶことができ、成長の機会を自分でつかめます。
さらに、ベテランエンジニアのサポートを受けられるチーム制の体制も整っています。開発プロセス全体を学びながら自然にリーダーを目指せる機会もあり、次のステップを考える方に適した環境です。
まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談をお試しください。自身に合ったキャリアの道を一緒に描いていきましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
フルスタックエンジニアとして活躍するために必要なスキルや知識

フルスタックエンジニアとして成長するには、開発の基盤から運用まで幅広い分野を身につけることが大切です。
フロントエンドではHTMLやCSSなどを使って画面や操作性を実現し、バックエンドではPythonやJava、PHPなどでデータ処理や業務ロジックを担います。
さらに、近年はAWSやAzureなどのクラウドサービスの理解がプロジェクトの効率化に直結します。
加えて、ネットワークやサーバー構築といったインフラ設計の知識があれば全体像を把握しやすくなり、Linuxを中心としたOSやデータベース、ミドルウェアの理解があれば安定した運用やトラブル対応にも強くなるでしょう。
プログラミングスキル
フルスタックエンジニアにとって、プログラミングスキルは土台となる重要な能力です。まず、フロントエンドではHTMLやCSS、JavaScriptを用いて見た目とユーザー体験を実装します。
バックエンドではPHP・Java・Pythonといった言語を使い、データ処理や業務ロジックを支えるための機能を構築します。
複数の言語に対応できれば、案件の幅が広がるでしょう。また、フレームワークやライブラリを活用することで開発効率も高まります。
HTML・CSS・JavaScriptなど、自分の目的やキャリアに合わせた言語選びが重要です。
クラウド技術に関する知識
クラウド技術は、フルスタックエンジニアにとって欠かせないスキル領域です。
主にIaaS(インフラ)、PaaS(プラットフォーム)、SaaS(サービス)といったサービス形態を理解し要件に応じた適切な選択や構成ができることが重要です。
企業がクラウド導入を進めるなか、こうした技術の深い理解はプロジェクトの成果を左右する要素となるでしょう。
インフラ設計・構築に関する知識

インフラ設計・構築の知識は、基盤を支えるエンジニアとして不可欠なスキルです。
フルスタックエンジニアに必要とされるのは、 要件に応じてどのサーバーや仮想化環境を選び、どう設計・導入するかを判断し、実際に構築・運用までできる実務能力です。
具体的には、ネットワーク・OS・ストレージ・コンテナなどインフラの多岐にわたる要素を俯瞰し、適切に組み合わせてサービスの土台を整備できる力が求められます。
さらに、設計の段階からセキュリティ方針を策定し、実際の導入とリリースまで推進した経験があると評価も高まります。
OSおよびミドルウェアに関する知識
フルスタックエンジニアにとって、OSとミドルウェアの理解は不可欠な基盤です。
OSとは、WindowsやLinuxなどコンピュータ上でほかのソフトウェアを動かす土台となるソフトウェアのことです。
ミドルウェアはそのうえに立ち、アプリとOSの橋渡しをする役割を持つソフトウェアで、ApacheやMySQLといった代表的な例が挙げられます。
具体的には、OSの基本操作やログの読み方を押さえることで、障害発生時の原因特定ができるようになります。
またミドルウェアの特性を理解することで、トラブルシュートやパフォーマンス調整が自力でできるようになり、開発・運用の両面で貢献しやすくなるでしょう。
フルスタックエンジニアに役立つ資格

フルスタックエンジニアを目指すうえで重要なのは、実装力に加えて上流工程を理解できる力です。
その証明として有効なのが国家資格のシステムアーキテクト試験と、ITストラテジスト試験です。前者は要件定義やシステム全体の設計力を問う内容で、ユーザーの要望に沿う力を磨けます。
後者は経営とITを結びつける視点を養い、事業戦略に基づくIT活用を提案できる力が評価されます。
どちらも難易度は高いものの、取得すれば実装者から設計・提案ができる人材へと成長し、キャリアの選択肢を広げる大きな後押しになるでしょう。
システムアーキテクト試験
システムアーキテクト試験は、スキルレベル4に位置づけられる難関資格です。
受験者には業務要件を分析し、システム全体の構造設計や要件定義を行い、設計を主導する能力が求められます。
合格することで、システム設計を牽引できる上流工程のプロとして信頼され、SE・PM・ITコンサルタントなど中核的なポジションへのキャリアパスも拓けます。
ITストラテジスト試験
ITストラテジスト試験は、企業のビジネス戦略と情報戦略を結びつけて推進できる高度人材を対象とする資格です。
試験を通じて求められる能力は事業や業務環境を分析し、それに基づいたIT戦略・システム化計画を構築・実行・評価するスキルであり、経営層や顧客に対して高度な提案ができる力が養われます。
フルスタックエンジニアとしてシステムを構築するだけでなく、事業の成長に直結する戦略立案や上流工程も担える人材として、市場価値が一気に高まります。
フルスタックエンジニアの年収相場

スタックエンジニアの年収相場は、雇用形態やスキルレベルによって大きく変動します。
正社員の場合、平均的な水準は5,500,000円〜6,500,000円程度で、経験や習熟度によって上下する傾向があります。
一方、フリーランスとして働く場合は案件単価が直接収入に反映されるため柔軟に報酬が上がりやすく、年収9,600,000円〜15,000,000円程度に達するケースも少なくありません。
総合的に見ると、幅広い経験を備えたフルスタックに近いスキルを持つエンジニアの年収は5,000,000円〜10,000,000円程度が目安とされ、国内平均年収である約4,430,000円と比較して高めに位置しています。
さらに上流工程への対応力やマネジメントスキル、資格取得など市場価値を示す要素を兼ね備えています。
正社員でも7,000,000円以上を狙うことが可能であり、フリーランスであればより大きな上積みを期待できるでしょう。
フルスタックエンジニアのキャリアパス

フルスタックエンジニアのキャリアパスは、一つの方向に限定されるものではありません。
まず、多様なキャリア展望があるからこそ、自分の強みや関心に応じた進路を描けるのがフルスタックエンジニアの大きな魅力です。
SESで培ったスキルを次のキャリアにつなげたい方は、一歩踏み出すことが大切です。
私たちテクニケーションでは、資格取得支援制度によるスキルアップの後押しや、各案件でリーダーを目指せる環境を整えています。
また、開発フロー全体を学びながら、自分の強みを活かせるキャリアを築ける点も特徴です。
自分に合う働き方を探したいと思ったらぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料でご相談ください。
選考ではなく、現状の悩みやキャリアの希望を気軽に話せる場であり、将来像を具体的に描くきっかけになります。
SES経験を次のステージへと広げたい方におすすめです。新たな可能性を一緒に見つけていきましょう。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
フルスタックエンジニアとして活躍するなら

フルスタックエンジニアとして力を発揮するためには、自分のスキルを活かしやすい環境を選ぶことが欠かせません。
特に案件選択制によって目指すキャリアに直結する業務に挑戦できること、チーム制で先輩エンジニアからサポートを受けられることは、安心感と成長の両方を得られる重要な条件です。
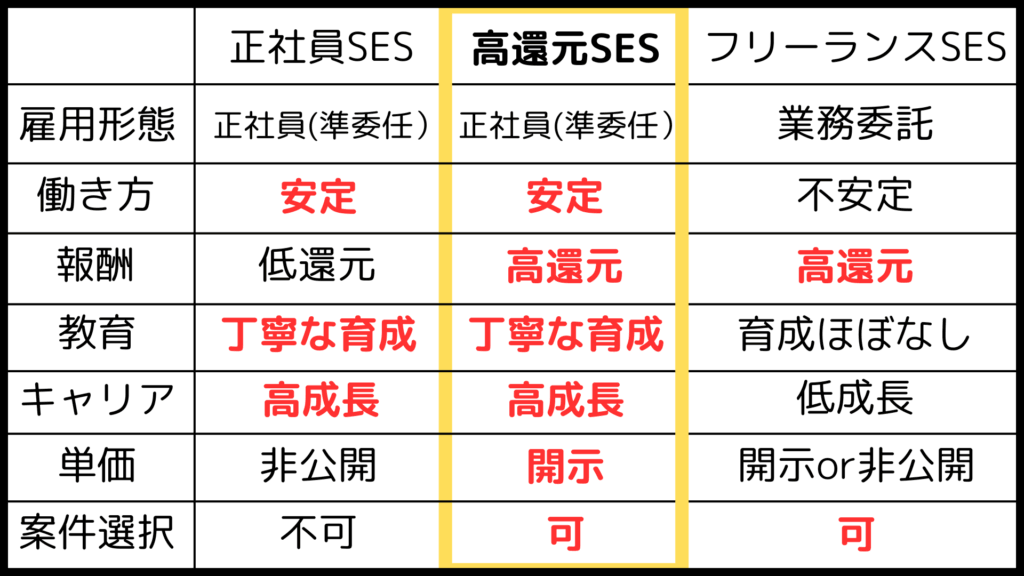
自分に合う案件でスキルを磨きたいという思いを持つ方には、私たちテクニケーションの環境がぴったりです。
案件選択制により、自分のキャリア目標に沿った案件を自由に選べるため、無理なく理想に近づけます。
またチーム制を導入しているため、ベテランエンジニアからの丁寧なフォローがあり、不安を抱えず挑戦を続けられます。
一人では得にくい実務経験やノウハウも自然と身につくでしょう。さらに、透明性のある仕組みやスキルアップ支援を活用すれば、市場価値を着実に高めることが可能です。
まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーにお気軽に無料相談してみませんか?現状の悩みや理想を共有することで、自分に合ったキャリアプランが見えてくるはずです。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!





















