Linux認定技術者試験資格とは?LPICとLinuCの違いや難易度、取得のメリットについて解説

現場でLinuxサーバーの運用や保守に携わっていても、それがどれほどのスキルなのかを外部に伝えるのは簡単ではありません。
経験があっても、履歴書や社内評価に反映されにくいという、もどかしさを感じている方も少なくないのではないでしょうか。
そのなかで注目されている資格の一つが、Linux認定資格です。
スキルの可視化やキャリアアップを後押しする手段として、資格の取得を考え始める方も増えています。
この記事では、LPICやLinuCなどのLinux資格の種類や難易度、取得後のメリットまでを解説します。次のキャリアを見つけるきっかけとして読み進めてみてください。
目次
Linux認定技術者試験資格とは

Linuxは、サーバーやシステム運用の中核を担うOSとして、長年インフラ業務を支えてきました。そのため、仕事で自然と関わる機会があった方もいるかもしれません。
しかし、知識や操作経験があっても、それを第三者に示す方法は限られています。そこで活用できるのが、Linux技術者向けの認定資格です。
代表的な資格には、LPIC(エルピック)とLinuC(リナック)があります。どちらも、Linuxに関する技術力を客観的に示すために設けられており、レベルごとの試験に分類されています。
LPICはカナダに本部を持つLPIが運営し、国際的に通用する認定資格です。一方、LinuCは日本市場に特化した認定制度で、LPI-Japanが主催しています。
どちらの資格も、インフラエンジニアをはじめとする技術者に向けた実践的な内容が中心です。
LPICとLinuCの違い
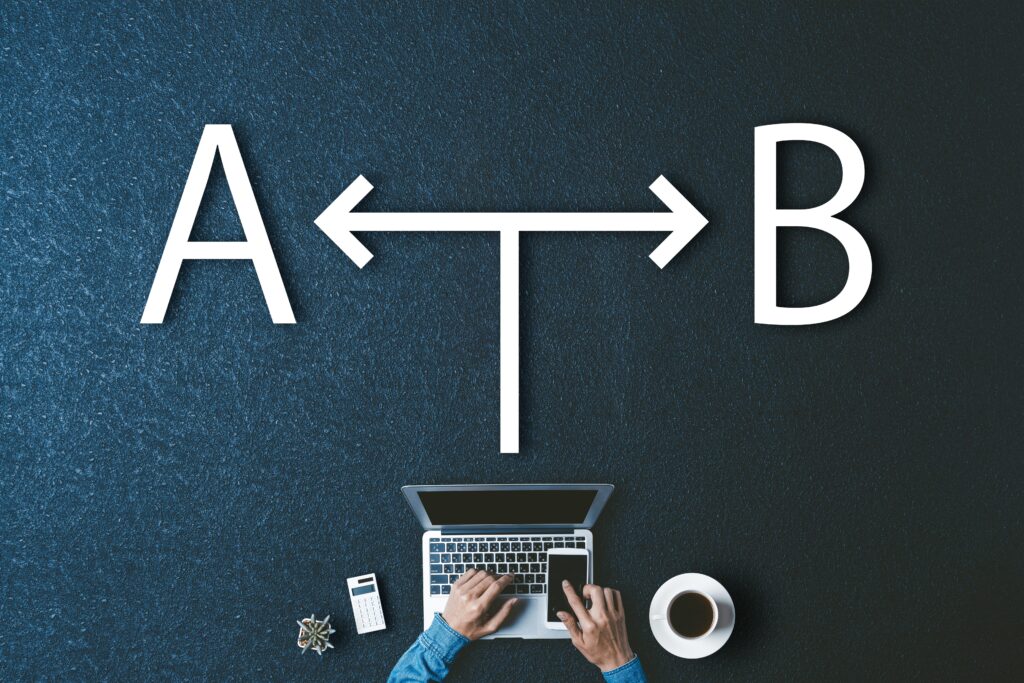
Linux資格として知られるLPICとLinuCは、いずれも実務スキルの証明となる認定制度です。共通点もありますが、試験の形式や主催団体、有効期限などに違いがあります。
どちらを選ぶべきかを判断するには、それぞれの特徴を整理し比較することが大切です。
試験の種類
LPICとLinuCはどちらも、習得レベルに応じた段階的な資格制度です。
LPICはLPIC-1からLPIC-3までの3段階に分かれ、上位になるほど専門性が高くなります。
LinuCもレベル1からレベル3まで用意されており、基礎から専門的な分野まで、段階を追って習得できるようになっています。
LPICはコマンドの仕様や用語の違いを見極める設問が中心で、知識の整理と設問意図を把握する力が求められるでしょう。
LinuCは、日本語で構成された実務シナリオに沿った出題が多く、操作の流れを思い浮かべながら答えやすい形式です。
資格区分

LPICは、レベル3で専門分野が分かれているのが特徴です。セキュリティや仮想化、ミックスド環境などのテーマ別に試験が用意されており、分野ごとに認定が得られます。
LinuCは、レベル1から順に全試験に合格していくことで、上位レベルの認定が得られます。
特定の領域に絞って取得したい方にはLPIC、基本から実務に必要な幅広い知識を段階的に身に付けたい方にはLinuCが適しているでしょう。
有効期限
LinuCには有効期限が設けられておらず、一度取得すれば再受験なしで資格を保有し続けることができます。
試験範囲の改定はありますが、実務から一時的に離れても資格が取り消されることはありません。
LPICは5年ごとの更新制です。技術の進化に応じて知識を更新していく仕組みで、継続的な学習が前提となっています。取得後も新しい動向を意識したい方に向いています。
LPICとLinuCの学習難易度

資格取得に向けた準備では、試験の難しさや取り組み方が気になる方も少なくないでしょう。
ここでは、それぞれの出題傾向や内容を比較し、自分に合った資格を検討する際の参考になるよう整理しています。
LPIC
LPICは出題範囲が広く、専門性の高い問題も含まれており、出題傾向を把握して計画的に取り組む工夫が必要です。
LPIC-1では基本的な操作を中心に問われますが、LPIC-2ではネットワークやセキュリティの実践知識が求められ、LPIC-3ではより高度なテーマ別分野に進みます。
仮想化やセキュリティなど、実務での知識がないと内容をイメージしにくく、未経験者は習得に時間がかかる傾向があります。
英語の設問を翻訳した問題文も少なくないため、読解に手間取ることがありますが、専門領域を絞って学びたい方には適した資格です。
LinuC
LinuCは日本の受験者向けに作成されており、試験問題はすべて日本語で出題されます。
内容も国内の実務環境を反映しており、日常的にLinuxを扱っている方にとって親しみやすい構成です。
初級から上級まで段階的に構成されており、レベル1ではユーザー管理やファイル権限、レベル2ではサーバーやネットワークが出題されます。レベル3ではクラウドや仮想環境の設定がテーマです。
業務でLinuxを扱っている方であれば、これまでの経験がそのまま学習に活かせる場面が豊富なため、知識が定着しやすいでしょう。
学習期間の目安としてはレベル1が1〜3ヶ月、レベル2が3ヶ月〜半年、レベル3は半年〜1年程度とされています。
独学でも学習しやすい点や、出題意図の明快さも含め、業務と並行しながら学習を継続したい方にとって取り組みやすい資格です。
Linux認定技術者試験の試験内容

Linuxの資格は複数あり、どれから学べばよいか迷う場面もあるでしょう。
ここでは主な試験の概要を整理し、目的や経験に応じて選択しやすくなるようまとめています。
LPIC-1
LPIC-1は、Linuxの基本操作に関するスキルを証明する初級資格です。
ユーザー管理やファイル操作、シェルの使い方などが出題され、101試験と102試験に分かれています。
これからLinuxを学ぶ方はもちろん、実務経験を振り返りたい場合にも役立つでしょう。
LPIC-2
LPIC-2では、ネットワーク設定やサーバー管理、セキュリティ対策など実践的な知識が問われます。
試験は201と202に分かれ、DNSやWebサーバー、ファイル共有などの項目が含まれます。
このレベルからの受験も可能ですが、認定を受けるには有効期限内のLPIC-1を保有していることが条件です。
LPIC-3
LPIC-3は、3つの分野に特化した上級資格です。
セキュリティ、仮想化と高可用性、混在環境管理の各試験があり1分野ずつ認定が得られます。受験は誰でもできますが、LPIC-2の認定があることがLPIC-3認定の条件です。
LinuCレベル1

LinuCレベル1は、Linuxの導入から基本操作までを体系的に学べる初級資格です。
ユーザーやファイルの管理、ネットワークの基礎などが中心で、101と102の両試験に合格すると認定されます。日本語での受験に対応しており、学習が始めやすいでしょう。
LinuCレベル2
LinuCレベル2は、業務で求められる中級レベルの知識や対応力が確認されます。
サーバー構築や障害対応、ログの読み取りやセキュリティの基本が出題対象です。LinuCレベル1を取得していなくても受験できますが、認定はレベル1取得後になります。
LinuCレベル3
LinuCレベル3は、仮想化やクラウド、可用性の高い構成などを扱う上級資格です。
試験は3分野に分かれており、いずれか一つの合格でレベル3認定が得られます。自分の興味や専門性に合った分野の受験が可能です。LinuCレベル2の認定後にレベル3も認定されます。
Red Hat認定資格

Red Hat Enterprise Linuxに特化した実技重視の認定制度です。
基本的な操作能力を確認するRHCSAと、ネットワーク構成や自動化を扱うRHCEが代表的です。
試験では、仮想環境でコマンドを実行しながら、与えられた課題に取り組む方法が採用されています。
Linux Foundation認定資格
Linux Foundationは、特定のディストリビューションに依存しない実技試験を提供しています。
LFCS(システム管理者)やLFCE(エンジニア)をはじめ、Kubernetes(沢山のコンテナをまとめて自動で管理運用してくれる仕組みのこと)やクラウド技術に対応した資格も取得可能です。すべてオンラインで受験できます。
Linux認定技術者試験取得のメリット

Linuxの資格に興味はあっても、「実務経験があれば十分なのでは」と感じる方は少なくありません。
しかし、資格の学習によって、現場経験だけでは触れる機会が少ない部分の知識を体系的に学ぶことが可能です。
ここでは、取得によって得られる具体的なメリットを紹介します。
世界で活躍できる資格が得られる
LPICやLinux Foundation認定資格は、世界基準でスキルを証明できる国際的な認定制度です。
Linuxは世界中のWebサーバーの56.6%以上で使われており、ITインフラの中心的存在です。
そのため、LPICやLinux Foundation認定資格は、海外案件や多国籍チームでも通用する知識として評価されます。
キャリアアップの機会に恵まれる
Linux認定資格を取得すると、構築や運用などの上流工程を任される場面が増え、担当領域の拡大につながることもあります。
評価制度に資格取得を取り入れている企業もあり、実績とあわせて評価されやすくなるでしょう。
「経験だけでは昇進に限界がある」と感じていた方には、資格取得がチャンスとなるかもしれません。
スキルの証明ができる
Linux認定資格は、実務で培ったスキルを第三者にわかりやすく示す方法になります。
採用や異動の際に、経験や知識を客観的に示せるかどうかで、評価に差が出るケースもあります。
信頼性の高い資格を持っていれば、経験を評価してもらいやすくなるでしょう。
転職で有利になる

Linux認定資格を保有していると、スキルレベルが明確になり、採用担当者の信頼を得やすくなります。
特に未経験からの転職や、高度な業務を目指す場合には、学習意欲や技術力の証明として評価されやすくなります。
求人票に資格保有者歓迎などの記載がある職種では、選考がスムーズに進むケースも少なくありません。
Linux認定資格を通じて得た知識やスキルは、現場での信頼に加え、今後のキャリアを広げるきっかけにもなります。
しかし、費用もかかることから取得に躊躇してしまう方もいるかもしれません。
私たちテクニケーションでは、LPIC-3をはじめとする推奨資格に対し、参考書や受験料の費用補助が受けられる資格取得支援制度を設けています。
受験料や教材費の一部が対象で、学習コストを抑えながら上位資格を目指すことが可能です。
また、合格後にはキャリア支援制度を通じて、スキルや目標に応じた案件の選択ができる案件選択制の仕組みがあります。
取得した資格を十分に活かすためにも、事前に希望する働き方やスキルの方向性を整理しておきましょう。
キャリアの次のステージを目指すなら、ぜひテクニケーションのカジュアル面談でぜひご相談ください。
Linux関連資格取得後のキャリアパス

Linux認定資格を活かすことで、運用業務から設計や構築フェーズへの移行や、専門性の高い職種へのステップアップが目指せます。
サーバーやネットワークの基盤構築に携わるインフラエンジニアを経て、SRE(Site Reliability Engineer)としてシステムの可用性や信頼性を支える道があります。
また、DevOpsの分野では開発と運用の連携を強化し、CI/CDの自動化や構成管理の最適化を担う役割が期待されるでしょう。
さらに、仮想環境やクラウド技術の理解があると、AWSやGCPなどクラウド基盤の運用や設計に関わるクラウドエンジニアとしての働き方も選べます。
中・長期的には、システム全体を管理するプロジェクトマネージャーや、セキュリティ領域のリードエンジニアへと役割を広げていくケースも少なくありません。
こうしたキャリアパスを現実にしていくには、働く環境が大きく影響します。
キャリア形成を支える環境として、私たちテクニケーションでは、エンジニアの志向や習得スキルに応じて案件を自由に選べる案件選択制を導入しています。
SREやクラウドエンジニアを目指す場合でも、ご自身に合ったプロジェクトで、必要な経験を段階的に積んでいけるでしょう。
また、各案件のリーダーを狙い、実務でマネジメント力を養うこともできます。
将来的にプロジェクトを統括する立場や、専門性を深めたポジションを目指す方にはステップアップの機会となるでしょう。
働き方やキャリアの方向性に迷ったら、カジュアル面談でご相談ください。履歴書は不要で、休日も対応しています。
Linuxの資格を取得してキャリアアップするために

Linux資格を取った後、そのスキルの活かし方で、どのようなキャリアに進めるかが変わってきます。
資格があることで業務の幅が広がる一方で、「このまま今の環境でよいのだろうか」と迷いが出てくることもあるでしょう。
どれだけ知識や技術を身につけていても、適正な評価が得られなければ、成長の手応えを感じにくくなるかもしれません。
私たちテクニケーションでは、こうした課題に応えるために、エンジニアの努力や成果を正当に評価できる仕組みを整えています。
単価給与連動制では、契約単価に応じて報酬が決まり、成果が収入に直結します。自分の働きがどう評価されているかが明確になり、納得感を持って業務に取り組むことができるでしょう。
また、案件単価の開示によって、契約金額と自身の報酬の内訳をはっきりと確認できます。報酬の根拠が見えることで、上司の主観に左右されない、公平な報酬体系を実感しながら働ける環境です。
さらに、テクニケーションは高還元SESとして、売上に対するエンジニアへの還元率も業界水準を上回る水準で設定しています。
報酬だけでなく、希望に応じた働き方を実現しやすいようサポート体制を整えています。
Linux資格を強みとして活かし、次のキャリアステップを考えている方は、ぜひ一度カジュアル面談をご利用ください。





















