インフラエンジニアは勉強嫌いでも大丈夫?なれる方法や勉強嫌い克服の対処法を解説

インフラエンジニアを目指す際に、「勉強が苦手だけど大丈夫だろうか」と不安を感じている方は少なくありません。
たしかに、技術の進化が速いIT業界では学び続ける姿勢が求められます。しかし勉強嫌いでも、工夫次第でインフラエンジニアとして活躍することは可能です。
この記事では、勉強が苦手な方でもインフラエンジニアを目指せる方法や、勉強嫌いを克服するための具体的な対処法を紹介します。
また、勉強をサポートしてくれる職場環境の選び方も解説するため、自分に合った学習方法と職場を見つける参考にしてはいかがでしょうか。
目次
インフラエンジニアとは

インフラエンジニアは、企業や組織のIT基盤を支える重要な役割を担う技術者です。
サーバーやネットワーク機器などのハードウェアから、それらを効率的に動かすためのソフトウェアまで、幅広い領域を担当します。
具体的にはシステムの設計や構築、運用や保守を行い、安定したシステム稼働を維持するために日々対応することが仕事です。
インフラエンジニアの需要は年々高まっており、クラウド化の進展やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、人材不足が加速しています。
そのため、未経験からでも挑戦しやすい職種として注目を集めています。
インフラエンジニアになるために必要な知識

インフラエンジニアとして活躍するためには、いくつかの基本的なIT知識やスキルが必要です。
一見すると多岐にわたる内容に思えるかもしれませんが、すべてを一度に身につける必要はありません。
効率的な学習方法を身につければ、勉強嫌いでも少しずつスキルアップしていくことが可能です。
何から始めればよいのかわからない方は、まず基礎的な知識を身につけることから始めましょう。
ネットワークやサーバーの基本概念を理解すれば、ほかの知識も徐々につながってきます。
ネットワーク技術に関する基礎知識
インフラエンジニアの基礎となるのが、ネットワーク技術です。IPアドレスやサブネットマスク、DNSなどの基本的な概念から、TCP/IPプロトコルスイートやルーティングなどの知識が必須となります。
ネットワークは複雑に見えても、一つひとつの要素は論理的につながっているため、基礎から順を追って学べばきちんと理解できます。
まずはインターネットの仕組みや、コンピュータ同士の通信方法といった基礎から学ぶと理解しやすくなるでしょう。
実際にルーターを設定したり、パケットの流れを確認したりする実践的な経験も役立ちます。
サーバー構築と運用の知識

サーバーの構築や運用は、インフラエンジニアの重要な業務です。物理サーバーの仕組みから仮想化技術、クラウドサービスに至るまで、幅広い知識を習得する必要があります。
基本的な構成要素を理解し、実際に環境を作ってみることが上達への近道です。
初心者は仮想マシンを使って、自分のパソコン上でサーバーを構築する練習から始めるとよいでしょう。
Linuxの基本操作やWebサーバーの設定など、実際に手を動かしながら学ぶことで理解が深まります。
またAWSやAzureなどのクラウドサービスの無料枠を活用すれば、本格的なサーバー環境も体験できるため、教科書だけでは得られない実践的な知識が身につきます。
シェルスクリプトおよびコマンド操作の理解
効率的なサーバー管理には、コマンドラインの操作が欠かせません。
WindowsならPowerShell、LinuxならBashなどのシェルコマンドを理解し、基本的なスクリプトを作成できる力が求められます。
最初は難しく感じても、少しずつ習得していけば問題ありません。
コマンド操作は使用頻度の高いものから少しずつ覚えていくとよいでしょう。
自動化のためのシェルスクリプトは、単純な処理から始めて徐々に複雑なものに挑戦すると挫折しにくくなります。
毎日少しずつコマンドを覚えていく習慣をつければ、いつの間にか多くのコマンドを使いこなせるようになり、作業効率も大幅に向上します。
情報セキュリティ知識
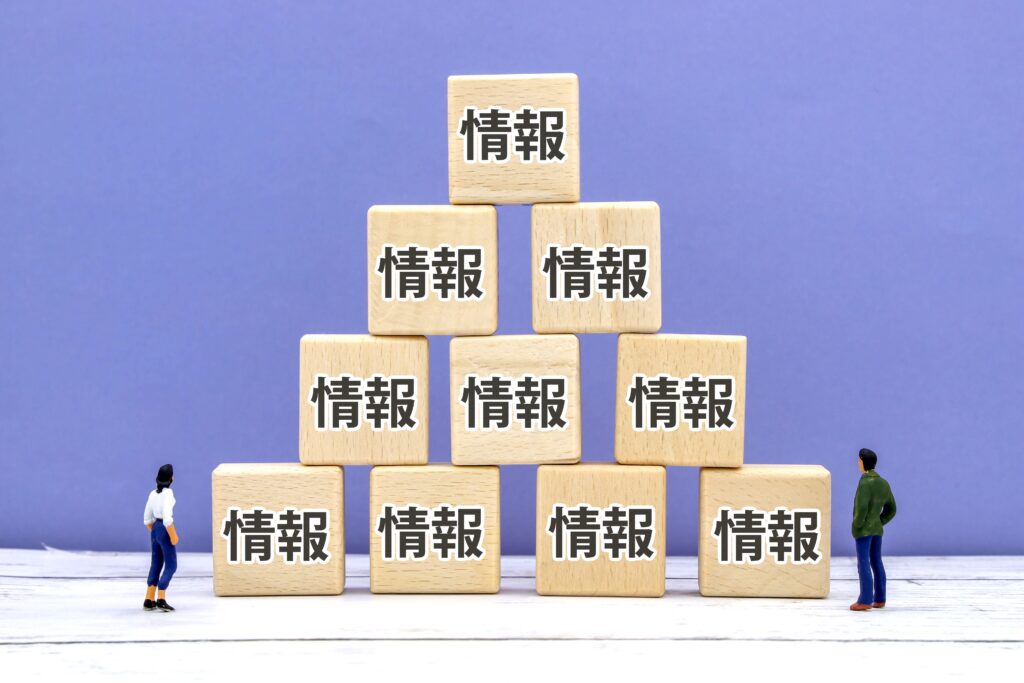
システムを守るためのセキュリティ知識も重要な要素です。ファイアウォールの設定やアクセス制御、脆弱性対策など、基本的なセキュリティ対策を理解する必要があります。
日々新しい脅威が登場する分野ですが、基本的な考え方を押さえておくことが大切です。
まずはCIAと呼ばれる機密性(Confidentiality)や完全性(Integrity)、可用性(Availability)の基本原則から理解を深めましょう。
また、セキュリティ関連のニュースに目を通す習慣をつければ、実際の脅威や対策について学べます。
プログラミングスキル
インフラエンジニアにも、ある程度のプログラミング知識が必要です。
特に自動化やクラウド環境では、コード化されたインフラ(Infrastructure as Code)の考え方が主流となっています。
基本的な文法やロジックを理解すれば、業務効率化に役立てられます。
言語としては、PythonやRubyなどの習得がおすすめです。特にPythonはシンプルで習得しやすく、自動化ツールも充実しています。
最初は複雑なプログラムではなく、小さな作業の自動化から始めると効果的です。
勉強嫌いだとインフラエンジニアになるのは難しい?

勉強が嫌いだけれど、インフラエンジニアになれるのだろうかと不安に思う方は少なくありません。結論からいえば、勉強嫌いでもインフラエンジニアになることは可能です。
ただし、ある程度の学習は避けられないため、効率的な学習方法を身につけることが鍵となります。
インフラエンジニアに求められるのは、暗記力よりも問題解決能力や論理的思考力です。必要な情報を見つけ出し、適用する力があれば、すべてを覚える必要はありません。
また、実務経験を通じて自然と知識が身につくこともあります。
勉強嫌いだとインフラエンジニアは難しい理由

勉強嫌いな場合、インフラエンジニアを目指すうえでいくつかの障壁があることも事実です。ここでは、勉強嫌いがインフラエンジニアの道に与える影響を解説します。
ただし、これらの障壁は工夫次第で乗り越えられるため、あきらめる必要はありません。
また、勉強嫌いを克服するためには、まず自分が勉強嫌いになった原因を理解することが大切です。
初期学習が厳しいため
インフラエンジニアになるためには、最初にネットワークやサーバーなどの基礎知識を身につける必要があります。
この初期学習の段階で躓くと、その先に進むのが難しくなるため、最初の壁を乗り越えることがとても重要です。
特に独学の場合は、何から手をつければよいかわからず途方に暮れることも少なくありません。
専門用語が多く登場するため、最初は理解するのに時間がかかります。勉強嫌いな方にとって、この初期の壁を乗り越えるのは大きな課題の一つです。
長期的なキャリアアップが難しくなるため

IT業界は技術の進化が速く、新しい知識やスキルを継続的に学び続けることが必要です。
勉強嫌いだと、この継続的な学習が苦痛に感じられ、長期的なキャリアアップが難しくなる可能性が出てきます。
クラウド技術やコンテナ技術など、次々と新しい技術が登場しています。学習をやめてしまうと時代に取り残されることがあるため、注意しましょう。
しかし、すべての新技術を追いかける必要はなく、自分の専門分野を深めることで価値を高めることも可能です。
効率的な学習方法を身につけ、必要な技術だけを選んで学ぶという戦略も効果的です。
企業から学習姿勢が評価されるため
多くの企業では、技術力だけでなく学習に対する姿勢も評価されます。勉強嫌いが原因で学習意欲が低いと判断されると、オファーや昇進の際に不利になる可能性も否定できません。
ただし、学習姿勢は勉強好きかどうかではなく、必要な知識を身につける努力をしているかどうかで評価されることがほとんどです。
勉強嫌いでも、業務に必要なスキルを着実に身につけていく姿勢があれば、十分に評価されます。
勉強嫌いでもインフラエンジニアになるには自己分析が必要
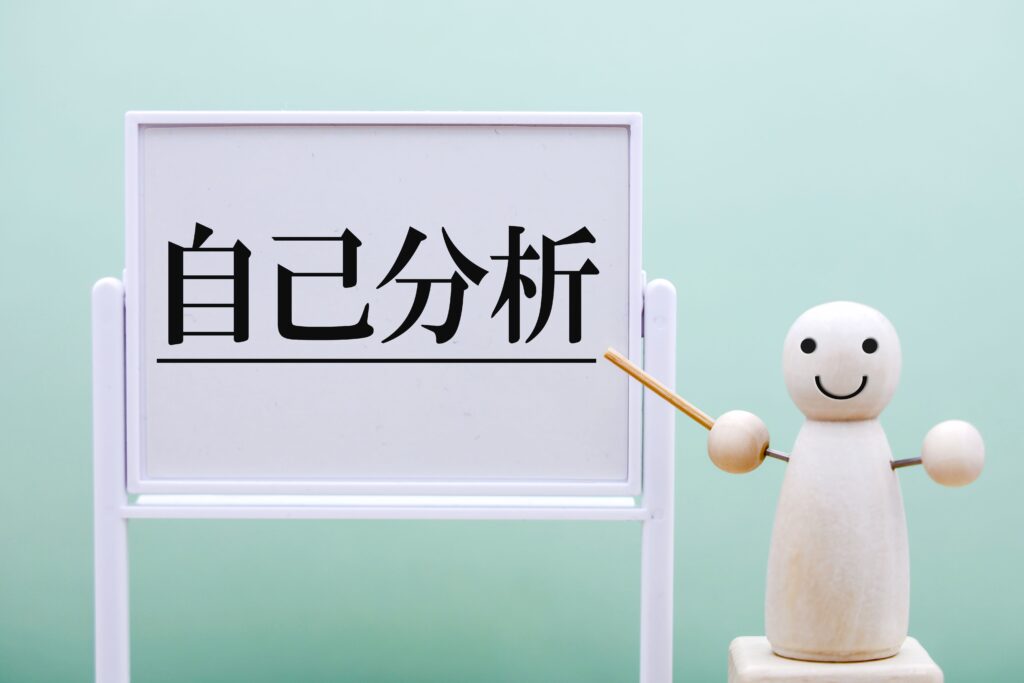
勉強嫌いでもインフラエンジニアになるためには、まず自分自身を知ることが大切です。なぜ勉強が嫌いなのか、どのような学習方法が自分に合っているのかを分析しましょう。
自己分析を通じて、効率的な学習方法を見つけることができれば勉強嫌いを克服する第一歩となります。
自己分析では過去の経験を振り返りながら、自分が何に興味を持ち、どのような環境で能力を発揮できるかを探ります。
この過程で、インフラエンジニアとしての適性も見えてくるでしょう。
勉強嫌いの原因を分析する
勉強嫌いにはさまざまな原因があります。過去の勉強で挫折した経験や、自分にあわない学習方法を強いられてきたことなどが考えられます。
なぜ勉強が嫌いなのかと自問自答してみることが大切です。
例えば長時間座って勉強するのが苦手、教科書を読むだけでは理解できない、一人で勉強するとモチベーションが続かないなど具体的な原因が見えてくるはずです。
原因がわかれば、それに対応した学習方法を探すことができます。
短時間で集中して学習する、実践を交えながら学ぶ、グループで学習するなど自分に合った方法を見つけることが重要です。
インフラエンジニアとしての適性を見極める

インフラエンジニアに向いている方には、いくつかの共通点があります。論理的思考力や問題解決能力、細部に注意を払う慎重さなどが挙げられます。
これらの特性が自分にどの程度当てはまるか考えてみることが有効です。
また、インフラエンジニアの仕事内容に興味を持てるかどうかも重要な判断材料となります。
サーバーやネットワークの仕組みに興味がある、システムの安定運用に携わりたい、トラブルシューティングが好きといった特性はありませんか。
こうした特性を持つ方は、インフラエンジニアとして活躍できる可能性は高いでしょう。
勉強が苦手だけれどインフラエンジニアを目指す方は、環境選びが重要です。
私たちテクニケーションは、エンジニアの単価に対する還元率が高い高還元SES企業として、エンジニアの希望やキャリアビジョンを大切にする職場環境を提供しています。
例えば、案件選択制により、実践的に学びながら成長できる案件を自分で選ぶことができます。
興味のある分野を選ぶことで、学習へのモチベーションも自然と高まりやすくなるでしょう。
また、チームでの協力体制も整っており、先輩エンジニアからのアドバイスを受けながら着実にスキルを伸ばせる環境です。
透明性を重視する姿勢も特徴的で、会社間の単価を開示することにより、自分の市場価値を正確に把握できます。
まずは気軽にテクニケーションのカジュアル面談でご相談ください。
勉強嫌いでもインフラエンジニアを目指すためにできること

勉強嫌いでも、工夫次第でインフラエンジニアになるための学習を進めることができます。
ここでは、勉強嫌いな方でも実践できる具体的な方法を紹介します。自分に合った方法を見つけて、無理なく続けることが成功への近道です。
学習を始める前に、自分の目標を明確にしておくことも欠かせません。
なぜインフラエンジニアになりたいのか、どのような分野で活躍したいのかという目的意識があれば、学習のモチベーションを保ちやすくなります。
自分に合った勉強方法を見つける
人によって効果的な学習方法は異なります。視覚的に理解するタイプや実践しながら学ぶタイプ、人に教えながら理解するタイプなど、自分の特性を把握して学習法を選ぶことが上達への近道です。
視覚的に理解するタイプなら、図解やイラストが豊富な教材や動画講座が効果的です。実践派なら、ハンズオン形式の教材や実際にサーバーを構築しながら学ぶ方法が向いています。
人に教えることで理解が深まるタイプなら、勉強会に参加したり、学んだことをブログにまとめたりする方法も有効です。
中長期的な目標を設定する

大きな目標をいきなり達成しようとすると挫折しやすくなります。
そのため、中長期的な目標と、それを達成するための小さな目標を設定することが継続の秘訣のポイントです。小さな成功体験が次への原動力になります。
例えば1年後にインフラエンジニアとして転職するという大きな目標がある場合は、3ヶ月以内にネットワークの基礎を理解する、半年以内に基本情報技術者試験に合格するなど具体的なステップに分けて取り組むことがおすすめです。
小さな目標を達成するたびに達成感を得られ、次の目標に向かうモチベーションになります。
資格取得に必要な時間を把握し学習計画を立てる

インフラエンジニアに関連する資格は、学習の指針として役立ちます。
資格取得を目指すことで、体系的に知識を身につけられるだけでなく、就職や転職の際にもアピールポイントになる利点があります。
基本情報技術者試験やLPIC(Linux技術者認定試験)などの資格は、インフラエンジニアの基礎知識を証明するものとして重要です。
これらの資格に必要な学習時間を調べ、自分のペースで計画を立てましょう。基本情報技術者試験なら100〜200時間程度の学習が必要といわれています。
1日1時間勉強するなら3〜6ヶ月、週末にまとめて勉強するなら数ヶ月で取得を目指せるため、無理のない計画が大切です。
また、勉強が苦手な方は、努力を支えてくれる環境に身を置くのがよいでしょう。
私たちテクニケーションでは、学習スタイルや目的に合わせて成長できる制度を整えています。
資格取得支援制度により、基本情報技術者試験やLPIC、AWS関連資格などの取得を目指す際も学習サポートが受けられます。
さらに案件選択制を導入しているため、学んだ知識を活かせるプロジェクトを自分で選ぶことが可能です。興味のある領域を実務で経験することで、学びが自然と身に付くでしょう。
またチーム制により経験豊富なメンバーと協力できるため、安心感を持って業務に取り組めます。自分の理解度に応じてサポートを受けられるため、計画的なステップアップが可能です。
自分に合った学び方が知りたいという方は、まずはテクニケーションのカジュアル面談でご相談ください。
インフラエンジニアになるための勉強嫌い対処法

勉強嫌いを克服するためには、学習に対する考え方を変えることが重要です。勉強というと堅苦しいイメージがありますが、好奇心を持って取り組めば楽しく学ぶことができます。
ここでは、勉強嫌いを克服するための具体的な方法を紹介します。
興味を持ちやすい分野から着手する
インフラエンジニアの仕事は幅広いため、まずは自分が興味を持てる分野から学び始めると効果的です。
好きなことから入れば、学習も苦痛ではなく楽しみになり、自然と知識が身についていきます。
ゲームが好きな方なら、自宅にゲームサーバーを構築してみるのもおすすめです。クラウドに興味があれば、AWSやAzureの無料枠を使って環境を作ってみることで実践的に学べます。
セキュリティに興味がある方なら、CTF(Capture The Flag)というセキュリティコンテストに参加してみるのも有効な方法でしょう。
適度に息抜きをしながら勉強する

長時間集中して勉強するのは誰でも大変です。短時間の集中と適度な休憩を組みあわせるポモドーロ・テクニックなどの時間管理法を活用すれば、効率的に学習を進められるでしょう。
25分勉強したら5分休憩するというサイクルを繰り返すことで、集中力を保ちながら学習を進めることが可能です。
また、勉強する環境も重要な要素です。カフェや図書館など、自分が集中できる場所で学習すると効果的でしょう。
音楽を聴きながら勉強するのが好きな方は、歌詞のない音楽を選べば集中力が高まります。自分に合った環境と時間配分で学習を進めることがポイントです。
自分にご褒美を与える
目標を達成したときに自分へのご褒美を用意しておくと、モチベーションを保ちやすくなります。
小さな成功体験を積み重ねることで、勉強への抵抗感も少しずつ薄れていくため、自分を上手に褒める習慣をつけるとよいでしょう。
1週間毎日勉強できたら好きな映画を見る、資格に合格したら欲しかったものを買うなど、自分が喜ぶご褒美を設定しておくと効果的です。
また、学習の進捗を記録することも有効な方法です。日記やアプリを使って学習時間や内容を記録すれば、自分の成長を実感できます。
スクールや勉強会を活用する

一人で勉強するのが苦手な方は、スクールや勉強会を活用するのが効果的です。
仲間と一緒に学ぶことで、モチベーションを維持しやすくなり、わからないことをすぐに質問できる環境が学習をサポートします。
プログラミングスクールやオンライン講座では、プロの指導を受けながら体系的に学べるメリットがあります。
勉強会やコミュニティに参加すれば、同じ目標を持つ仲間と知識を共有することも可能です。
質問や相談ができる環境があると、わからないことで躓いたときも前に進みやすくなります。
私たちテクニケーションは、チーム制によって経験豊富なエンジニアが常に身近にいるため、分からないことがあってもその場で相談しながら進めることが可能です。
また、実践を通じて自然に学べる案件が豊富にあり、自分の興味や目的に合わせて案件を選べる案件選択制を導入しています。
例えば、クラウドに関心があればAWS構築案件、ネットワークに興味があればオンプレ環境の構築案件を選ぶことが可能です。
さらに、資格取得支援制度を活用することで、勉強が苦手でも目標に向けて無理なく計画を立てられる体制が整っています。
あなたも自分らしく活躍できる環境を探してみませんか?まずはカジュアル面談で、これまでの経験や今後のキャリアビジョンについてお話しください。
インフラエンジニアとして働くための注意点

インフラエンジニアとして働くうえで意識しておきたいポイントがいくつかあります。これらを理解しておくことで、より円滑にキャリアを進めることができます。
勉強嫌いな方でも、仕事を通じて自然と学べる部分もあるため、まずは基本的な心構えを身につけることが肝心です。
インフラエンジニアの仕事は、企業や組織のIT基盤を支える重要な役割です。そのため、責任感や危機管理意識が求められます。
また、チームで協力して問題解決にあたることも多いため、コミュニケーション能力も欠かせません。
技術面だけでなく、これらの点も意識して働くことで、インフラエンジニアとしての価値を高めることができます。
勉強嫌いな方がインフラエンジニアとして働きやすい職場

勉強嫌いな方がインフラエンジニアとして成功するためには、自分に合った職場環境を選ぶことも重要です。
サポート体制が整っていたり、自分のペースで成長できたりする環境があれば、勉強嫌いでも徐々にスキルアップしていくことが可能になります。
職場選びの際には、技術的な面だけでなく、人間関係や働き方のスタイルも考慮することが大切です。
質問しやすい雰囲気があるか、無理なく働ける環境か、自分の成長をサポートしてくれるかなどさまざまな角度から検討してみましょう。
案件選択ができる職場
自分のスキルや希望に合った案件を選べる環境は、勉強嫌いな方にとって大きなメリットです。
適切な難易度の案件を選ぶことで、無理なく成長しながら自信をつけていけるため、長期的なキャリア形成に役立ちます。
自分のペースでスキルアップできる環境は、勉強嫌いな方にとって理想的な職場といえます。
チームで協力し合える職場

一人で抱え込まず、チームで協力して問題解決できる環境も重要な要素です。わからないことを気軽に質問できる雰囲気があれば、勉強嫌いでも自然と知識が身につき、成長のスピードも早まります。
チーム制を採用している職場では、経験豊富なリーダーのサポートを受けながら業務を進められる点が大きな強みです。
勉強が苦手でも、職場の環境次第で自然に成長していけるのがインフラエンジニアという仕事です。
私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりのスタイルに合った働き方を大切にしています。たとえ勉強が得意でなくてもスキルアップできる仕組みを整えています。
まず案件選択制により、自分のスキルレベルや興味に合った案件を選ぶことができるため、無理なくステップアップが可能です。
難易度が適切な案件に携わることで、実務を通して自然と学べるのがポイントです。
また、チーム制によるサポート体制も整っており、経験豊富なエンジニアと協力しながら業務を進めることができます。
わからないことはその場で質問できるため、一人で悩まずに学べる安心感を持って働けるでしょう。
「勉強が苦手でも少しずつ成長していきたい」という方こそ、まずはカジュアル面談でご相談ください。あなたに合った働き方を一緒に探していきましょう。
勉強嫌いを克服して働きやすい職場を見つけよう

勉強嫌いを克服し、自分に合った職場を見つけることで、インフラエンジニアとしての道は大きく開けます。
この記事で紹介した方法を参考に、自分に合った学習方法と職場環境を見つけてはいかがでしょうか。
勉強嫌いだからといって、インフラエンジニアを諦める必要はありません。
自分の特性を理解し、効率的な学習方法を身につければ、少しずつスキルアップしていくことは十分に可能です。
また、サポート体制が整った職場環境を選ぶことで、勉強の負担を軽減しながらキャリアを築いていけます。
高還元SES企業であるテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりの個性や将来ビジョンを大切にした職場環境づくりに力を入れています。
興味のある分野や難易度に応じて案件を選べる案件選択制を導入しているため、苦手意識を抱かずに自分のペースで無理なくスキルアップが可能です。
経験を積むことでチームメンバーから各案件のリーダーへステップアップする道も開かれており、マネジメントスキルも習得できるでしょう。
チーム制による日常的なサポート体制があるため、わからないことを気軽に相談できる雰囲気が整っており、安心感を持って働けます。
報酬は案件単価に応じて決定される単価給与連動制を採用しており、実力がある方ほど高収入を得やすい環境です。
あなたも自分らしく活躍できる場所を探してみませんか?まずはテクニケーションのカジュアル面談にご相談ください。





















