インフラエンジニアの運用保守業務とは?仕事内容から市場価値まで解説!

インフラエンジニアとして日々運用・保守を担っているものの、「このままの働き方でよいのだろうか」と将来に不安を感じていませんか。
サーバーやネットワークの安定稼働を支える運用保守は、企業の基盤を守る重要な役割を担っています。
しかし、その重要性とは裏腹に成果が見えにくく、障害が起きて初めて注目されることも少なくありません。
そのため、評価が上がりにくい・年収が伸びにくい・キャリアの選択肢が限られているといった悩みを抱える方もいるのが現状です。
本記事では、インフラエンジニアの運用保守の具体的な仕事内容・求められるスキル・年収相場・将来性について解説します。
自身の市場価値を見直し、より適した働き方を考えるヒントも紹介しますので、キャリアについて悩んでいるという方の参考になれば幸いです。
目次
インフラエンジニアの運用保守業務とは?

インフラエンジニアの業務は、システムやネットワークが安定して稼働するために欠かせません。
特に運用と保守の業務は日常的に行われ、システムの安定稼働を支える基盤となっています。
運用では主に日々の監視やメンテナンスを通じて安定性を維持し、保守では障害対応や改善策の実施など問題解決に直結する作業を担います。
これらは密接に関わり合っており、組織全体のIT環境を守るために欠かせない業務です。
インフラエンジニアの運用業務
運用業務は、ITインフラを安定して動かし続けるための日常管理を中心に行う仕事です。
サーバーやネットワーク機器の稼働状況を常時監視し、異常や性能低下が発生していないか確認します。
また、システムのパフォーマンスを維持するための調整・ログの収集・分析による問題の早期発見も重要な役割です。
さらに、定期的なバックアップやセキュリティチェックを行うことで、万が一の障害や情報漏えいを未然に防ぎます。
これらの基本的な業務を適切に行うことで、システムトラブルの未然防止や安定稼働につながり、企業の業務を支える役割を果たせるでしょう。
インフラエンジニアの保守業務

保守業務は、発生した障害の解決やシステム改善を行う役割です。
例としてサーバーダウン・ネットワーク障害といったトラブルが起きた際に迅速に原因を特定し、復旧対応を実施します。
復旧後は問題の再発防止に向けた改善策・パッチ適用・機器交換・設定変更といった改善策を講じます。
さらにハードウェア・ソフトウェアの更新や、セキュリティリスクへの対応も保守業務に含まれており、常に新しい環境を維持することが大切です。
保守業務は単なる修理にとどまらず、システムを継続的に進化させ、より強固で信頼性の高いIT基盤を構築していくための活動といえます。
インフラエンジニアの運用と保守の違い
運用と保守はしばしば混同されますが、運用はシステムを正常に動かし続けるための管理で、保守は問題が発生した際の復旧や改善といった位置付けです。
つまり、運用は日常的な予防的活動、保守は事後的な対応が中心となります。ただし両者は切り離せない関係にあり、安定したシステム運用には両方のバランスをとることが不可欠です。
インフラエンジニアは状況に応じて運用と保守を柔軟に行い、企業のIT基盤を守る重要な役割を果たしています。
インフラ運用の仕事内容

インフラ運用は、システムやネットワークを安定稼働させるために行う継続的な業務です。
具体的には、サーバーやネットワーク機器の稼働監視・定期的なメンテナンス・バックアップの取得・リカバリ対応などがあります。
これらの作業を通じて障害を未然に防ぎ、業務システムの安定性と信頼性を確保することが目的です。
日々の細かな作業が企業の基盤を支えており、インフラエンジニアの役割のなかでも特に継続性が重視される領域といえます。
システムの稼働監視業務
稼働監視は、サーバー・ネットワーク・データベースなどのシステム基盤が正常に稼働しているかをリアルタイムで確認する業務です。
専用の監視ツール(Zabbix・Nagios・CloudWatchなど)を用いて、CPU使用率・メモリ消費量・ストレージの空き容量・ネットワークの通信状況などの指標をリアルタイムでチェックします。
異常値やエラーログを検知した場合は、原因の切り分けや一時対応を行い、大規模障害に発展する前に速やかな対応が必要です。
監視業務はトラブルの早期発見に直結するため、システム全体の安定性を維持するうえで欠かせません。
金融機関やECサイトなどの24時間365日稼働が必要な企業環境では、わずかな遅延や停止が企業の信用や収益に直結するため、迅速かつ正確な監視対応が求められます。
近年ではAIによる予兆検知や自動通知の仕組みも導入されており、稼働監視業務は単なる監視にとどまらずシステム全体の安定を守る砦としての役割を担っています。
定期的な点検・メンテナンス

点検・メンテナンスは、システムを長期的に安定稼働させるために計画的に行う作業です。
サーバーやネットワーク機器のログを確認し、エラーメッセージやパフォーマンス低下の兆候を早期に発見します。
不要データやキャッシュを整理し、ディスク容量やメモリ使用率を適切化することも重要です。
また、OS・ミドルウェア・アプリケーションのバージョンを定期的に更新し、セキュリティパッチを適用することで脆弱性を放置しない体制を作ります。
さらに、アクセス制限やファイアウォール設定を見直し、内部からのリスクに備えることも必要です。
点検を定期的に実施することで潜在的なトラブルを未然に防ぎ、障害発生率を低減できます。
クラウドや仮想化環境の普及により、物理機器だけでなく仮想サーバーやクラウドリソースも対応に含まれています。
そのため、今後ますます物理運用における予防的活動として欠かせない業務となるでしょう。
バックアップおよびリカバリの対応
バックアップとリカバリの対応は、障害や災害が発生した際にシステムやデータを迅速に復旧するために必須の業務です。
定期的にデータやシステム環境をバックアップし、オンプレミス環境だけでなくクラウドやリモート拠点にも複製を補完することで、リスクを分散します。
また、実際に障害(サーバーダウン・データ破損・ランサムウェア攻撃)が発生した場合には、バックアップデータを用いて復旧作業を行い業務への影響を抑えます。
特に金融・医療・製造業のように業務をストップできないシステムを扱う現場では、ダウンタイムが数分でも莫大な損失につながるため、堅牢なバックアップ体制が求められます。
さらに、定期的なリストアテストを行い、復旧作業が確実に機能するかを確認することも欠かせません。
特に近年はサイバー攻撃や自然災害のリスクが高まっており、堅牢なバックアップ体制と迅速なリカバリ手順はインフラ運用の信頼性を支える重要な要素です。
インフラ保守の仕事内容

インフラ保守は、トラブル対応・改善提案・セキュリティ対応などを担う目立ちにくいもののシステムを根底から支える重要な役割です。
上記の業務は評価されにくい仕事ではありますが、実際には企業活動を止めないために必要であり、信頼を得るための仕事となっています。
保守業務に真摯に取り組むことは、確かな価値を持つプロフェッショナルな仕事だといえるでしょう。
システム障害への対応
システム障害への対応は、保守業務のなかでも緊急性が高く、企業活動のなかでも責任が伴う業務です。
障害発生時にはまず監視ツールやログを用いて現状を把握し、障害の範囲や深刻度を瞬時に判断します。
次に原因を切り分けながら復旧作業を実行し、できる限り短時間で通常稼働へ戻すことが求められます。
特に金融機関やECサイトなどのシステムでは数分の遅れが大きな損失につながるため、冷静な判断と的確な対応が求められます。
障害対応は普段は目立たない業務ですが、障害時に迅速にシステムを復旧することで、利用者や企業からの信頼を築くことができるでしょう。
さらに単なる復旧で終わらせるのではなく、障害後に原因を究明し、再発防止策を提案・実装することもシステム担当者の責務です。
迅速な行動力と改善への姿勢を併せ持つことで、企業のIT基盤を守る最後の砦としての役割を果たせます。
エラーや不具合に対する改善提案

保守業務では、単に発生したエラーや不具合を修復するだけでなく、同じ不具合を繰り返さないための改善提案力が必要です。
例えば、設定値の不整合で障害が発生した場合はパラメータの適切化を、システム構成にボトルネックがある場合にはネットワークやサーバーの再設計を検討する必要があります。
根本的な原因にアプローチすることでシステム全体の安定性や処理性能を向上させ、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
こうした改善活動はユーザーからは気付かれにくいですが、長期的には障害発生率の低減・ダウンタイムの削減・運用コスト削減といった成果を得ることが可能です。
また、自動化ツールの導入やクラウド環境への移行など、新しい技術を活用した提案が評価されるケースも増えています。
改善提案は守りだけでなく攻めの姿勢を持つ保守業務であり、企業のIT戦略全体を底上げできる大変価値の高い取り組みでしょう。
セキュリティ対策の実施
インフラ保守においてセキュリティ対策は、企業の信頼性を守るための根幹を担っています。具体的な業務は、OSやアプリケーションの脆弱性に対するパッチ適用・ユーザーアカウントやアクセス権限の管理・不正アクセスの検知・遮断などです。
特に近年はサイバー攻撃の巧妙化が進んでおり、ランサムウェアやゼロデイ攻撃といった高度な脅威に備える必要があります。
定期的なセキュリティの見直しやペネトレーションテストの実施が不可欠です。また、オンプレミスだけでなくクラウドサービスを利用するケースが増え、ゼロトラストモデルの導入やSOC(セキュリティオペレーションセンター)との連携も求められています。
利用者には見えにくい業務ですが、情報漏えいやシステム停止を未然に防ぐことは企業の信用や事業継続性を守る大切な役割を果たしています。
システムセキュリティの担当者には常に更新されるセキュリティ知識をキャッチアップし、積極的に対策を強化する姿勢が求められるでしょう。
インフラエンジニアの運用業務に必要なスキル

運用の現場では日々業務を行うことで、多くの専門的スキルが身についていきます。監視・点検・障害対応といった作業の裏には、技術的な知識やシステム全体を把握する力が必要です。
これらは経験を積み重ねることで着実に蓄積され、将来のキャリアに活かせる強みとなります。
自身のなかに眠るスキルを言語化することで、日々の業務が成長に直結していることを実感できるでしょう。
技術系スキル
運用業務には、ネットワーク・サーバー・データベースといった幅広い技術知識が必要です。
サーバーの負荷を調整するためには性能監視やOSの知識を要し、ネットワーク障害の切り分けはプロトコルや機器設定に関する理解を深めなければいけません。
さらにスクリプト作成による業務効率化や、自動化ツールの活用も技術スキルの一部です。こうしたスキルは日常業務を通じて自然に磨かれており、キャリアアップに直結する大きな資産となります。
システムの情報把握スキル
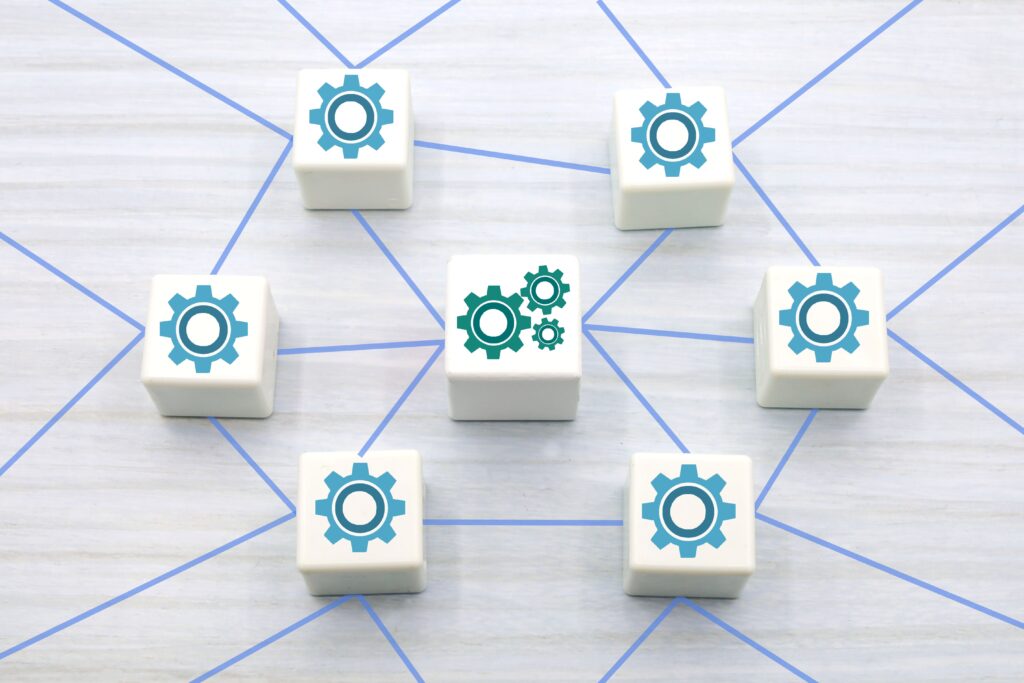
運用現場では、システムの全体像を把握し、どこに問題が潜んでいるかを素早く見抜く力が求められます。
サーバーやネットワーク、アプリケーションといった複数の要素を関連づけて理解できることは、障害対応のスピードと質を大きく左右するでしょう。
このスキルは単なる知識ではなく、日々の監視やトラブル対応を通じて培われる実践的な力です。
自身では意識しづらいかもしれませんが、情報把握能力はIT全般のキャリアに活かせる強力なスキルといえます。
インフラエンジニアの保守業務に必要なスキル

保守業務は障害対応や改善提案など、即時性と正確性が求められる仕事です。
そのため、トラブルに冷静に対処する力・コミュニケーション力・原因を突き止め再発防止につなげる分析力が重要です。
これらのスキルは一朝一夕では身につかず、日々の現場経験を通じて培われていきます。
裏方に見えがちな業務ですが、習得したスキルはどのIT分野でも活用できる強力な武器になるでしょう。
トラブル対応スキル
システム障害やエラーが発生した際に、迅速かつ冷静に対応できる力は保守業務の根幹です。問題の切り分けを行い、影響範囲を把握し、復旧を迅速に実現するスキルが求められます。
限られた時間で正しい判断を下すためには、幅広い技術知識に加え、過去の経験や事例から学ぶ姿勢も重要です。
トラブル対応は大きなプレッシャーを伴いますが、成功体験を積むことで確かな自信と信頼につながります。
コミュニケーションスキル

保守業務ではエンジニア同士の連携だけでなく、利用部門や経営層など技術に詳しくない方とのやり取りも発生します。
そのため、状況をわかりやすく説明し、必要な協力を得るコミュニケーションスキルが必要です。
障害対応時には迅速な情報共有が復旧スピードを左右し、改善提案を行う際には納得感のある説明が実現につながります。
技術力だけでなく、信頼関係を築く力も保守エンジニアにとって重要な武器となります。
分析スキル
単に障害を解決するだけでなく、原因を深掘りして再発防止につなげる分析力は、保守業務において付加価値の高いスキルです。
ログや監視データを読み解き、トラブルの根本原因を明らかにすることで、システム全体の信頼性向上に貢献できます。
さらに、障害の傾向を把握して予防的な施策を打てるようになると、一歩進んだ攻めの保守を実現可能です。
分析スキルは、経験と学習の積み重ねで磨くことができる専門性の高い能力でしょう。インフラエンジニアに欠かせないのは、日々の経験を次の成長につなげる環境です。
私たちテクニケーションでは、案件選択制により自分の得意領域や挑戦したい技術に合ったプロジェクトを選択可能です。
さらに、経験豊富な先輩と取り組めるチーム制が整っており、実務を通じてスキルを磨けます。
単価に応じて給与が決まる単価給与連動制もあるため、単価アップに応じて収入アップを目指すことが可能です。実力のあるエンジニアほど高い報酬を得やすいシステムが整っているため、高いモチベーションを維持しながら実務経験を積むことができます。
スキルを伸ばしつつ報酬アップを目指したいという方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
インフラエンジニアの年収相場
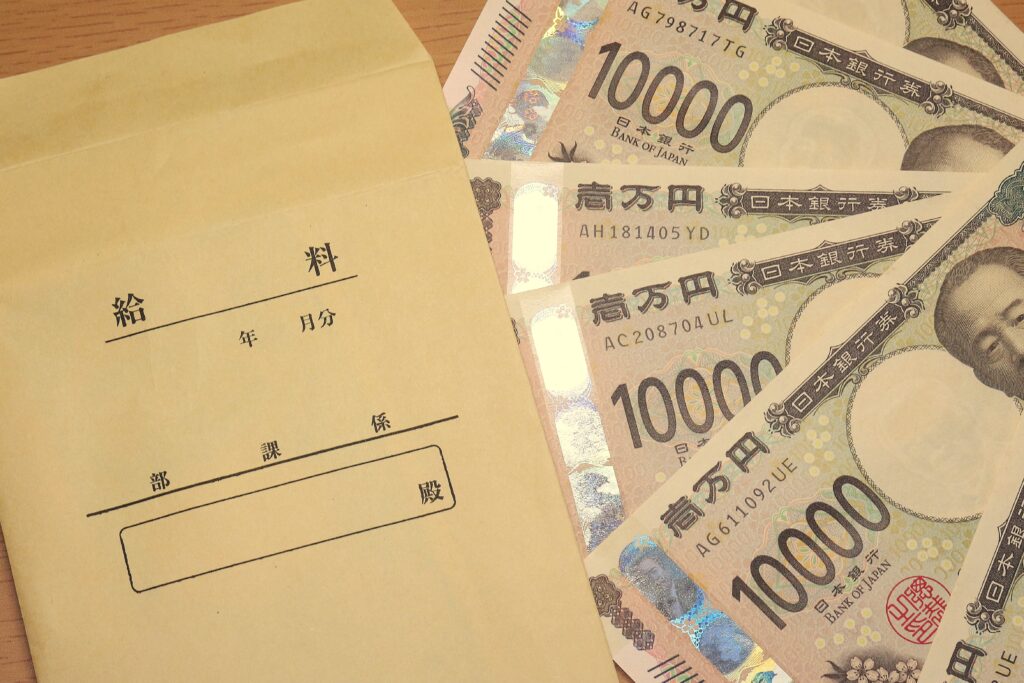
インフラエンジニアの年収は、経験・スキル・勤務先の規模・業界によって幅があります。
未経験から運用・保守に携わる場合は年収3,000,000〜4,000,000円程度が一般的です。
しかし、経験を積みサーバーやネットワークの設計・構築に関われるようになると、5,000,000〜6,000,000円台も期待できるでしょう。
さらに、クラウド・セキュリティに強みを持つエンジニアは需要が高く、年収7,000,000円以上を狙うことも可能です。キャリアの進め方次第で大きく収入アップが見込める職種です。
インフラエンジニアの運用保守業務に役立つ資格

資格は知識の裏付けとなり、自身のスキルを客観的かつ効果的に示す手段です。
資格は基礎的なIT知識を証明するものから、特定の技術分野に特化したものまで幅広く存在します。
資格取得の過程で学ぶ知識は実務にも直結し、業務効率化や障害対応の質を向上させることが可能です。ここでは、キャリア初期から中堅エンジニアまで活かせる代表的な資格をご紹介します。
基本情報技術者
基本情報技術者試験は、ITエンジニアを目指すうえで登竜門的な位置づけとなる国家資格です。
ネットワーク・データベース・セキュリティといったインフラに直結する分野をはじめ、プログラミング・アルゴリズムなどの幅広い知識が問われます。
保守業務に携わるエンジニアにとってはシステム全体の仕組みを理解し、障害の切り分けや原因分析に役立てられる点が大きなメリットです。
また、学習中に学ぶ理論は日々の業務に直結するため、業務効率化や改善提案の説得力を高める効果もあります。
ITパスポート
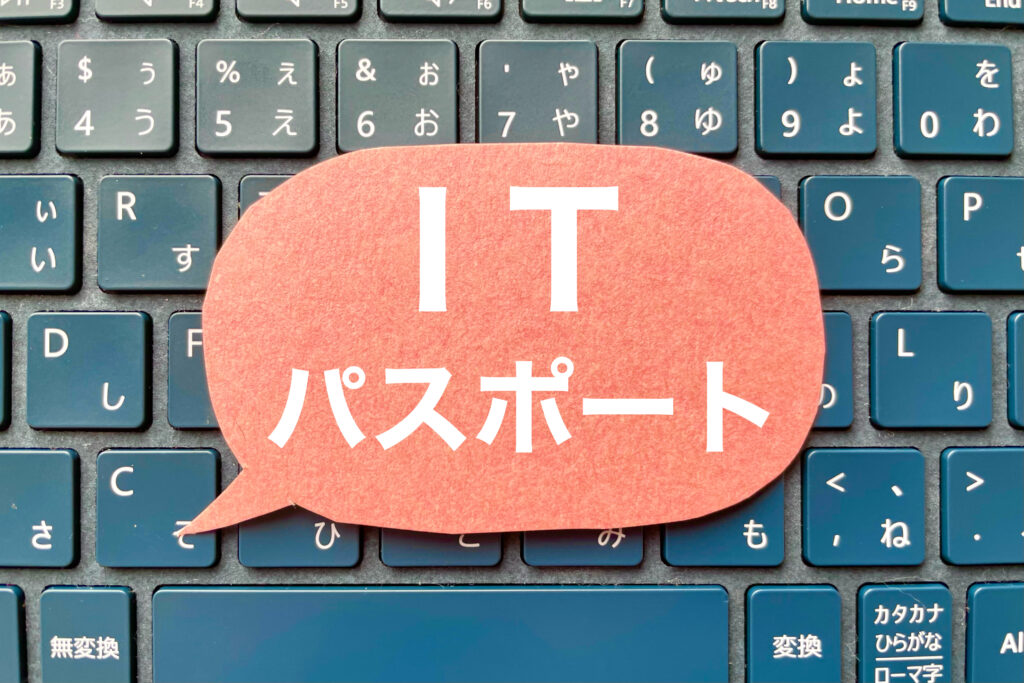
ITパスポート試験は、IT業界に携わるすべての方を対象とした国家資格で、ITの基礎知識を幅広く学べるのが特徴です。
難易度は初級程度で、未経験者やキャリアの初期段階にある方でも挑戦しやすく、これからインフラ運用保守を始めたい方に適しています。
出題範囲はシステムやネットワークに関する知識に加え、経営戦略・マネジメント・セキュリティ分野まで網羅しています。
そのため、単なる技術者としての知識にとどまらず、業務全体を理解する力が養われるでしょう。
マイクロソフト認定資格プログラム
マイクロソフト認定資格プログラムは、WindowsサーバーやMicrosoftAzureに関連する技術スキルを証明できる国際的な認定資格です。
運用保守の現場ではWindowsサーバー環境を扱う機会が多く、またクラウド活用が急速に進むなかでAzureの運用スキルは高く評価されます。
資格試験は役割ごとに体系化されており、サーバー管理者・セキュリティ担当・クラウドアーキテクトなど、自身のキャリアに合った分野を選択できます。
取得することで新しい技術にも対応できるエンジニアとしての証明になり、社内外での評価や市場価値の向上につながるでしょう。特に今後クラウド領域に進みたい方におすすめの資格です。
Linux技術者認定試験

Linux技術者認定試験は、サーバー環境で広く使われているLinuxの運用・管理スキルを証明できる資格です。
ユーザー管理・アクセス制御・シェルスクリプトを用いた自動化・セキュリティ設定など、保守業務に直結する知識が体系的に問われます。
LinuxはWebサーバーやアプリケーション基盤で主流であり、習得しておくと即戦力としての評価が高まります。
試験は段階的にレベル分けされているため、自身のレベルにあわせてスキルアップが可能です。
インフラエンジニアの年収はスキル次第で大きく変わります。私たちテクニケーションでは単価給与連動制を導入しており、プロジェクトの単価に応じて収入が上がる仕組みを整えています。
さらに資格取得支援制度でスキルを磨きながら、需要の高いクラウドやセキュリティ領域へ挑戦することも可能です。
経験を積みたい方には自由に案件を選べる案件選択制もあり、キャリアと収入を両立できる環境が整っています。
経験豊富な先輩から学べるチーム制も整っており、安心感を持ってキャリアを伸ばせるのも魅力です。
効率的にキャリアアップをしていきたい方は、ぜひ一度テクニケーションの無料相談をご利用ください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
インフラエンジニアにおける運用保守の将来性

インフラの運用保守は、自動化やクラウドの普及によって単純作業が減少しつつあります。
しかし、その一方でシステム環境は複雑化し、障害対応やセキュリティリスクへの備えといった高度なスキルの価値は高まっています。
特にクラウド環境の運用管理・セキュリティ強化・DX推進に伴う新技術の活用などは今後も需要が拡大する分野です。
将来性がないと思われがちな領域ですが、新しい技術と結びつけて学ぶことで、市場価値の高いエンジニアとして活躍し続けられるでしょう。
市場価値を高めたい場合、働きながらスキルアップも叶えられる環境に身を置くのがおすすめです。
運用保守の仕事は単純作業が減り、クラウドやセキュリティなど新しい技術に触れる機会が増えています。こうした変化に対応できるかどうかが、将来性を大きく左右します。
私たちテクニケーションでは案件選択制や単価給与連動制を採用しており、自身の得意分野の案件に取り組みつつスキルに見合った給与を得ることができます。
さらに、経験豊富な先輩と連携できるチーム制があるため、新しい領域でも安心感を持って成長可能です。
資格取得支援制度があるので、新しい技術を学び続けスキルを伸ばすこともできます。
自身の市場価値を高めたいと感じている方は、ぜひ私たち一度テクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
インフラエンジニアの運用保守を目指すには

運用保守を目指すには、ITの基礎知識を学ぶことから始めるのが効果的です。ITパスポートや基本情報技術者などの資格を活用し、ネットワークやサーバー、セキュリティの基礎を身につけると理解が深まります。
未経験からでも監視業務やヘルプデスクを経てキャリアを積み、徐々に高度な運用・保守へとステップアップする道もあります。
また、クラウドや自動化スキルを磨くことで将来的なキャリアの幅も広がるでしょう。継続的に学び、経験を重ねる姿勢が大切です。
私たちテクニケーションでは、専門のキャリアアドバイザーによる無料相談を行っています。働きながらスキルアップできる環境が整っており、さらにステップアップしたい方に適している環境です。
さらに高還元SESを掲げるテクニケーションでは案件選択制や単価給与連動制を取り入れており、自身の得意とする分野でスキルを活かして働きつつ、仕事量に見合った給与を得ることができます。
会社間の単価はエンジニアに開示しているため、透明性のある評価制度でモチベーションを保ちながら納得して働くことが可能です。
主体性を持ちながら働ける環境に身をおきたい、スキルを磨きながらしっかり稼ぎたいと考えている方は、ぜひ一度テクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談をご利用ください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
インフラ運用保守業務でスキルアップしたいなら

インフラ運用保守業務は、日々の監視や障害対応など一見評価されにくい仕事ですが、システムの安定稼働を支える不可欠な役割です。
基礎的な知識や資格取得を積み重ね、クラウド・セキュリティなど新たな分野にも挑戦すれば、市場価値を高められます。さまざまな経験を積んでおくことで、将来のキャリアアップへとつなげられるでしょう。
私たちテクニケーションでは、働きながらでも一人ひとりが成長できるよう、教育機会の提供やスキル取得のための援助を積極的に実施しています。
案件選択制で挑戦したい領域に進み、資格取得支援制度でスキルを強化することも可能です。
さらに単価給与連動制で成果が直接収入に反映されるため、やりがいを持って働ける環境が整っています。
経験豊富なベテランエンジニアからのサポートやチームメンバーと連携できるチーム制があるため、新しい領域でも安心感を持って挑戦できる環境です。
インフラ運用保守業務に携わりたいという方は、私たちテクニケーションのチームで一緒に働きませんか?ぜひ一度、無料相談で自身の希望の働き方やキャリアプランをお聞かせください。
簡単30秒!専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!





















