開発効率を劇的に改善!実践タスク管理と分からないことの質問術
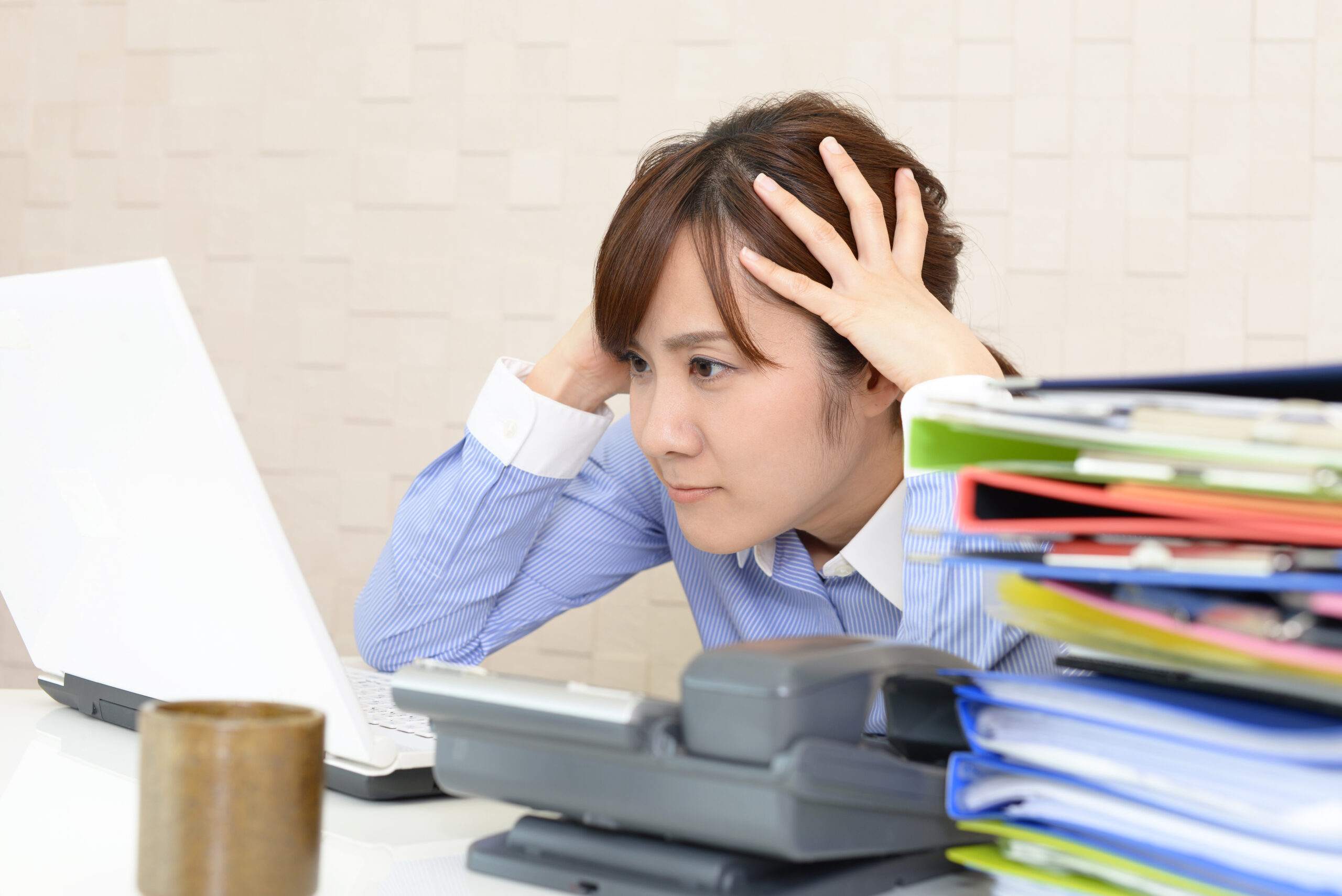
エンジニアとして働いていると、「気づいたら時間だけが過ぎていた」「何に時間を使ったのか分からない」という経験はありませんか?特にリモートワークや一人での作業が多いと、タスクの優先順位が曖昧になり、生産性が下がってしまうことも。
本記事では、実際の現場で効果を感じた「タスク管理の工夫」と「質問の仕方」について、具体的に紹介していきます。
目次
タスク管理は“見える化”が命

タスクリストではなく「やることログ」をつける
ToDoリストを作っても、終わらないまま溜まっていく…そんな悩みはありませんか?おすすめなのは、「やったことログ」と「やることログ」をセットで残す方法です。
•やることログ:今日の朝、これからやる予定のタスクをざっくり書き出す
•やったことログ:実際にやった作業を記録していく(こまめに)
これを1日の終わりに見返すと、「想定外の調査に時間がかかった」「集中できたタスクはどれか」など、自分の作業の傾向が見えてきます。振り返りが習慣化すると、次第に無駄な作業が減り、効率が上がっていきます。
優先度は「緊急×重要」で判断する
タスクが山積みになると、どれから手をつけるか悩んでしまいがち。そんなときは、いわゆる「緊急度×重要度マトリクス」でざっくり分類しましょう。
緊急 重要 対応
○ ○ 最優先で取り組む
○ × できるだけ早く対応
× ○ 時間を確保してじっくり
× × 後回しorやらない選択も
これをざっくりでもいいので頭に入れておくと、判断スピードが上がり、迷いが減ります。
「分からない」を武器にする質問術
「何が分からないか分からない」を脱するコツ
初心者に限らず、「何が分からないか分からない」と感じることは誰にでもあります。そんな時は以下のような問いかけを自分にしてみましょう。
•そもそも何をしたかったのか?
•何を試して、どうなったのか?
•エラーや挙動のどこが予想と違ったのか?
こうした問いを言語化することで、頭の中が整理され、自力で解決できるケースも増えてきます。
質問するときの「3つの型」
質問は、相手の時間をもらう行為でもあります。だからこそ、質問の仕方を工夫することで、答えがもらいやすくなり、結果として自分の作業も早く進みます。以下の「3つの型」は特に有効です。
1.現状の説明:今どのような作業をしていて、どこで詰まっているか
2.試したこと:自分で試した内容や、調べたキーワードなど
3.聞きたいこと:具体的に何を知りたいのか
例:
「〇〇画面のAPI呼び出しを実装中ですが、CORSエラーが出てしまい原因が分かりません。Access-Control-Allow-Origin について調べて、バックエンド側の設定を確認したのですが解決しませんでした。他に確認すべきポイントはありますか?」
このように質問できれば、的確なアドバイスをもらいやすくなり、結果的に学びも深まります。
タスク管理 × 質問術で得られる効果

この2つを意識して実践することで得られるメリットは多くあります。
•自分の進捗を正しく把握できるようになる
•無駄な時間が減り、集中すべき作業に注力できる
•分からないことを溜め込まず、早めに解決できる
•チーム内でのコミュニケーションがスムーズになる
開発現場で成果を出すためには、コードの知識だけでなく、こうした「進め方のスキル」も非常に重要です。
まとめ
開発効率を高めるためには、日々のタスクを見える化して自分でコントロールすること、そして分からないことを効果的に質問する力が鍵となります。
これらを意識するだけで、同じ仕事でも「疲労感」と「達成感」がまるで変わってくるはずです。
今日から実践できることばかりなので、ぜひ試してみてください。





















