アジャイル開発とウォーターフォール開発の違いとは?特徴や進め方を比較・解説

現場でアジャイル開発やウォーターフォール開発という言葉を耳にしても、各々の違いや特徴をきちんと理解できていないエンジニアは意外と少なくありません。
手法ごとの進め方や適性を把握しておくことは、スムーズな業務遂行だけでなく、今後のキャリア選択にも大きく関わってきます。
本記事では、アジャイル開発とウォーターフォール開発の考え方やプロセス、メリットや使い分けのポイントなどを解説します。
手法を理解し、今の案件の意味や自分に合った働き方のヒントが見つかれば幸いです。
目次
アジャイル開発とは

アジャイル開発とは、仕様の変更や追加が発生しやすいプロジェクトに対応するために生まれた柔軟な開発手法です。
短いサイクルで開発とフィードバックを繰り返す反復型のスタイルを取り、顧客や利用者とのコミュニケーションを重視します。
初期段階で全体を固めるのではなく、必要に応じて都度軌道修正しながら進めるのが特徴です。
また、Webサービスやスタートアップの案件などに導入されていることがあり、現場レベルでの意思決定や対応力が求められます。
スピード感と柔軟性を活かし、変化に強いプロジェクト運営を可能にするのが、アジャイル開発の大きな魅力です。
ウォーターフォール開発とは

ウォーターフォール開発は、要件定義・設計・実装・テスト・運用といった工程を上から順に一方向に進めていく、直線型の開発手法です。
各工程を完了してから次の段階へ移行するため、全体の進行管理がしやすく、ドキュメントを重視した明確な設計のもとで開発を進められます。
要件が初めから固まっている大規模案件や、堅牢性が重視される業務システムなどで採用されており、安定した品質を担保しやすい点が強みです。
上流工程の精度が後の成果を大きく左右するため、初期段階での綿密な設計と見通しが重要となる開発スタイルです。
アジャイル開発の特徴

アジャイル開発は計画通りに進めることよりも、変化への適応や価値あるプロダクトの提供を重視する考え方に基づいています。
従来の手法に比べて開発メンバーの自律性やチーム内の連携も重要視されており、現場ごとの判断や改善がしやすいのも特徴です。
次項では、アジャイル開発の進め方や現場対応のポイントを整理して解説します。
短いサイクルで開発を進める反復型
アジャイル開発では短い期間で、設計や実装、テストを繰り返す反復という進め方を採用します。
反復する進め方は、イテレーションと呼ばれることもあります。
一般的には1〜2週間単位で成果物をつくり、フィードバックを受けながら軌道修正していくのが特徴です。
反復型の手法により、大きな手戻りを防ぎながら柔軟に開発を進めることができます。
常に小さな単位で成果を積み重ねていくことで、仕様の曖昧な案件や変化の激しい現場にもスピード感を持って対応しやすくなるのがメリットです。
顧客や利用者とのコミュニケーションを重視する体制
アジャイル開発では、顧客や利用者との継続的なコミュニケーションを通じて、ニーズを的確に反映させながら開発を進めます。
初期に決めた仕様に固執するのではなく、対話を重ねるなかで得られるフィードバックをもとに、柔軟に対応する姿勢が重視されます。
開発チームが顧客と同じ目線に立ち、頻繁に認識をすり合わせながら進行することで、最終的な成果物の満足度を高めることが可能です。
こうした体制により、実際の利用シーンに即したプロダクトを提供しやすくなるのがアジャイル開発の強みです。
要件変更に柔軟に対応できる仕組み
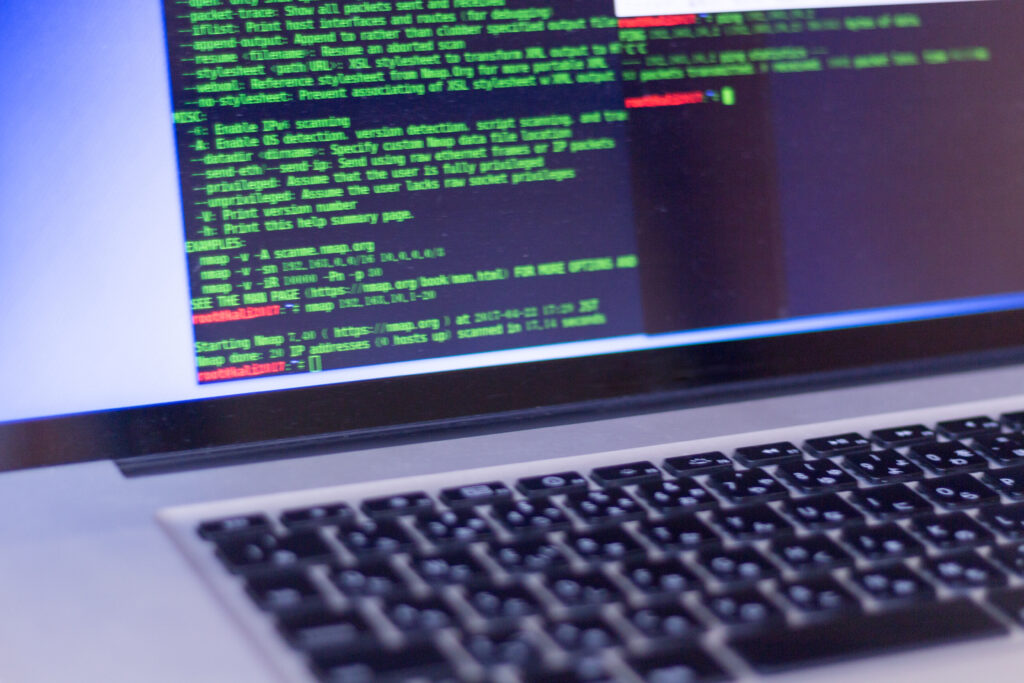
アジャイル開発では、開発途中での要件変更を前提にプロジェクトが設計されています。
市場やユーザーのニーズは常に変化するため、初期の仕様に固執するよりも、状況に応じて柔軟に方向修正できることが求められます。
定期的な振り返りやレビューの機会が設けられており、変化を即座に反映できる体制が整っているのが特徴です。
こうした仕組みによって、開発の手戻りや無駄を抑えつつ、ユーザーの満足度が高いプロダクトを継続的に届けることが可能になります。
ウォーターフォール開発の特徴

ウォーターフォール開発は、計画性や安定性を重視する現場で採用されてきた開発手法です。
あらかじめ決められたスケジュールや手順に沿って進行するため、進捗管理や工程間の責任分担が明確になりやすいのが特徴です。
想定外の変更が少ないプロジェクトや、大規模な案件などに適しており、堅実な開発体制を築きやすい点が評価されています。次項では、ウォーターフォール開発の特徴を解説します。
工程を順番に進める直線的なモデル
ウォーターフォール開発では、要件定義から設計・実装・テスト・運用までの工程を順に進めていく直線型のモデルを採用しています。
各フェーズを完了してから次の工程へ進むため、プロジェクト全体の進行状況が把握しやすく、計画通りに進めやすいのが特徴です。
一度完了した工程に戻ることは原則としてないため、スケジュールや予算を固定しやすく、一定の制約条件のなかでしっかりとした成果を出す場面に適しています。
工程ごとの役割分担も明確で、大規模プロジェクトでも管理しやすい点が強みです。
ドキュメントを重視するプロセス

ウォーターフォール開発では、各工程で作成されるドキュメントがプロジェクトの根幹を支えます。
要件定義書や設計書、テスト仕様書などを通じてプロジェクトの全体像や作業内容が明文化されるため、認識のズレを抑えることができます。
また、工程ごとの記録がしっかり残るため、途中でメンバーが入れ替わっても引き継ぎがスムーズに行えるのも特徴です。
情報を文書で管理すると、品質と再現性の高い開発を実現できるため、組織的な体制で安定した成果を求めるプロジェクトに適しています。
上流工程での計画が成果を左右する
ウォーターフォール開発では、プロジェクトの初期段階にあたる上流工程の計画や設計が、後の成果を大きく左右します。
要件定義や基本設計の精度が高ければ高いほど、下流工程での手戻りが少なくなり、スムーズな進行が可能です。
一方で、初期の見落としや要件の曖昧さがあると、後の工程で大きな修正が必要となるリスクもあります。
そのため、ウォーターフォール開発では最初の段階で徹底的に要件を整理し、プロジェクト全体の流れを設計する力が必要です。
上流工程でしっかりと計画を立て、ブレのない開発を進めたい方にとって、ウォーターフォール型の開発は魅力的な選択肢です。
しかし、プロジェクトごとに求められるスキルや体制は異なり、自分の強みを発揮できる環境を見極めることがキャリア形成には欠かせません。
もし、自分が今いる環境で理想のキャリア形成が難しいと感じている方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。
私たちテクニケーションでは案件選択制を採用しており、自分のキャリア形成や目標に応じた案件に取り組むことが可能です。
またチーム制を採用しており、経験豊富なリーダー層がスキルアップをフォローするため、効率的なスキルアップを目指せます。
スキルや経験を活かせる環境にチャレンジしたい方や、自分の価値に見合った働き方を目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
簡単30秒!
専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
アジャイル開発とウォーターフォール開発の主な違い

アジャイル開発とウォーターフォール開発は、進め方や管理手法が大きく異なる開発スタイルです。
明確なメリットと課題があるため、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った働き方を見極めることが重要です。
次項では両手法の違いをプロセスや対応力、納期意識や顧客との関わり方といった視点から解説します。
開発プロセスの進め方の違い
アジャイル開発は、小さな単位で開発と検証を繰り返す反復型のプロセスを通して、柔軟かつスピーディに進めるのが特徴です。
段階的に成果物を積み重ねるため、途中での仕様変更にも対応しやすく、改善を重ねながら開発が進行します。
一方ウォーターフォール開発は、要件定義から設計・実装・テストまでを一方向に進める直線的なスタイルで、各工程を順に完了させていきます。
初期段階で全体を設計し、計画通りに開発を進めることで、進行管理や品質の担保がしやすくなる点が特徴です。
要件変更に対する対応力の違い
アジャイル開発は、開発中に要件が変わることを前提に設計されており、仕様の追加や変更にも柔軟に対応できます。
短いサイクルでフィードバックを反映しながら進行するため、変化の激しい環境でも対応力を発揮しやすいのが特徴です。
一方ウォーターフォール開発は、工程ごとに内容を確定して進めます。
途中での大幅な変更には不向きであり、手戻りやスケジュールへの影響が大きくなる傾向があります。
成果物や納期に対する考え方の違い

アジャイル開発では完成度よりも、まず動くものを素早く提供し、ユーザーの反応を見ながら改善を繰り返す考え方が基本です。
納期はある程度柔軟に設定され、変化に対応しながら価値ある成果物を段階的に提供していきます。
一方ウォーターフォール開発では、計画段階で成果物の内容と納期を明確に定め、スケジュール通りに完了させることが重視されます。
品質や進行管理はしやすい反面、途中で仕様を見直すのが難しく、柔軟な調整には向いていないのが特徴です。
顧客や利用者との関係性の違い
アジャイル開発では、顧客や利用者と継続的にコミュニケーションを取りながら開発を進めていくのが特徴です。
定期的なレビューやフィードバックを通じて、現場の意見をすばやく取り入れ、プロダクトに反映していきます。
一方ウォーターフォール開発では、開発の初期段階で要件を確定し、後のフェーズでは顧客との関与が限定的になる傾向があります。
そのため、仕様のズレが発生しにくい一方で、柔軟な調整は難しくなるケースもあるでしょう。
開発中も顧客と頻繁にやり取りしながら調整していくのが得意な方もいれば、事前にしっかり要件を固めて着実に進めたい方もいるはずです。
自分の特性に合った開発スタイルで働くことは、パフォーマンスの向上にもつながります。
もし、自分に合った開発スタイルがわからない方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。
私たちテクニケーションでは、キャリアや価値観に応じて案件を自由に選べる案件選択制を導入しており、適性を模索しながらスキルを磨くことが可能です。
さらに、スキルアップを後押しする資格取得支援制度も採用しており、ご自身が磨きたいスキルを現場で実践しながら伸ばすことができます。
顧客との関係性や働き方を大切にしつつ、自分のスキルや経験に合った案件に参画したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。
簡単30秒!
専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
アジャイル開発のメリット

アジャイル開発は、従来の開発手法に比べて柔軟性と迅速性に優れており、変化が激しいプロジェクトなどに適しています。
チーム全体で協力しながら進めるスタイルや、継続的な改善を前提としたプロセスによって、開発効率や品質向上にもつながるのが特徴です。次項では、アジャイル開発の具体的なメリットを解説します。
早期に動くソフトウェアを提供できる
アジャイル開発では短い期間で開発やテスト、レビューを繰り返すイテレーションを用いるため、初期段階から動くソフトウェアの提供が可能です。
はじめから完成形を目指すのではなく、まずは必要なだけの機能を実装したバージョンをリリースし、実際の利用を通じて改善を加えていきます。
このアプローチにより、プロダクトの方向性を早期に確認できるうえ、関係者からの評価や要望をスピーディに反映しやすくなります。
結果として、開発効率の向上と無駄な工数の削減にもつなげることが可能です。
顧客満足度を高めやすい

アジャイル開発では、開発中も顧客や利用者と定期的にコミュニケーションを取りながら進めるため、ニーズの変化やフィードバックを迅速に取り入れることができます。
リリース後に不満やズレが生じる前に、段階的な改善を積み重ねることで、最終的な成果物の満足度を高めやすいのが特徴です。
また、進捗や成果が可視化されて共有されるため、顧客も信頼感を得られます。
双方向の関係性が構築されることで、信頼関係が生まれ、長期的なプロジェクトでも満足度の高い開発体験を提供しやすくなります。
ウォーターフォール開発のメリット

ウォーターフォール開発は古くから現場で活用されてきた手法であり、手順が明確に定まっている点から、組織的に進めやすい利点があります。
各工程の役割が明確で、複数の関係者が関わるプロジェクトでも作業の分担がしやすく、トラブル時の対応も整理しやすいのが特徴です。
次項では、ウォーターフォール開発が持つ具体的なメリットを解説します。
全体の進行管理がしやすい
ウォーターフォール開発では、各工程があらかじめ明確に定義されており、上流から下流へと順に進める直線的な開発モデルを使用しています。
進捗状況を工程単位で把握しやすく、計画通りに進んでいるかを客観的に判断しやすいのが特徴です。
また、全体のスケジュールやリソースの管理も事前に立てた計画に基づいて行えるため、複数の関係者が関わる大規模なプロジェクトにおいても統制が取りやすくなります。
こうした特性から、進行管理に高い精度が求められる案件でも信頼されている手法です。
大規模プロジェクトに適している

ウォーターフォール開発は、全体の工程をあらかじめ明確に定義し段階的に進めるため、大規模プロジェクトとの相性がよい手法です。
複数のチームや関係者が関わるプロジェクトでも、共通の設計書やドキュメントをもとに進めることで役割や作業範囲が明確になり、混乱を防ぎやすくなります。
また、スケジュールやコストの見通しが立てやすいため、開発の計画性や品質管理を重視する現場での活用も可能です。
このような特徴から、特に公共系や金融系など、安定性を重視する分野で使用されています。
ウォーターフォール開発のように計画性と安定性を重視する現場もあれば、アジャイルのように柔軟性を求める現場もあります。
どちらが優れているかではなく、自分のスキルや志向、得意とする働き方に合った開発スタイルを選ぶことが重要です。
もし、今請け負っている案件が自分に合っていないと感じることがあれば、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーにご相談ください。
私たちテクニケーションでは案件選択制を採用しており、ご自身の開発スタイルに合わせた案件を選ぶことが可能です。
そのため、ご自身の磨きたいスキルや、臨むキャリア形成に繋がる案件に挑戦することができます。
さらにチーム制を採用しているので、未経験の開発スタイルでもベテランエンジニアからサポートを受けながら進めることができます。
自分に合った環境や開発スタイルを見つけたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。
簡単30秒!
専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
アジャイル開発とウォーターフォール開発の使い分け

アジャイルとウォーターフォールは、各々が異なる特徴を持つ開発手法であり、プロジェクトの内容や環境によって適した使い分けが求められます。
一方が常に優れているわけではなく、目的や制約条件に応じて選ぶことが重要です。
次項では、プロジェクト規模や要件の明確さ、開発期間や予算などの観点から両手法の使い分け方を解説します。
プロジェクト規模による判断
開発手法を選ぶ際は、プロジェクトの規模が重要な判断材料となります。
小〜中規模のプロジェクトでは、仕様変更や方向転換が発生しやすく、柔軟に対応できるアジャイル開発が効果を発揮します。
短いサイクルでの開発と改善を繰り返すことで、限られたリソースのなかでもスピード感を持って成果を出すことが可能です。
一方で、関係者や工程が複雑な大規模プロジェクトでは、工程ごとの役割を明確にしやすいウォーターフォール開発が有効です。
全体像を把握しながら、段階的に着実に進めることができるため、管理や統制が取りやすく品質の安定にもつながります。
要件の明確さ・不確実さによる判断

開発手法を選ぶうえで、プロジェクト開始時点での要件の明確さや不確実さも重要な判断基準となります。
要件が初期段階で明確に定まっており、仕様変更の可能性が低い場合には、ウォーターフォール開発が適しています。
工程ごとに計画を立てて着実に進めるため、事前に全体を設計しやすく、進行管理や品質管理にも適した構造です。
一方で、ユーザーのニーズやビジネス要件が変化しやすい環境では、アジャイル開発の柔軟性が強みを発揮します。
開発の途中でも仕様変更を前提とした体制が整っているため、不確実性が高いプロジェクトでも臨機応変に対応できます。
各々の特性を理解すると、自分のプロジェクトに合った手法を適切に選ぶ判断材料となるでしょう。
開発期間や予算の制約による判断
開発手法を選ぶ際には、開発期間や予算の制約も大きな判断基準となります。
限られたスケジュールのなかで機能を早くリリースしたい場合や、顧客の反応を見ながら段階的に改善していきたい場合には、アジャイル開発が効果を発揮します。
小さな単位で開発を進めるため、初期費用を抑えながら柔軟に対応できる点がメリットです。
一方で仕様が明確で変更のリスクが少なく、あらかじめ定められた予算や納期のなかで着実に成果を出したい場合には、ウォーターフォール開発が適しています。
事前に計画と見積もりを立てやすく、管理コストの抑制や品質の安定にもつながります。予算や納期の制約が厳しいプロジェクトほど、手法の選定が結果を左右するでしょう。
ハイブリッド開発

現代の開発現場では開発規模や目的、関係者の体制が多様化しており、単一の開発手法だけでは対応しきれないケースも増えてきました。
こうした背景から従来の枠にとらわれず、柔軟に開発を進めるアプローチとして、ハイブリッド開発が注目されています。
プロジェクトごとの特性に応じて、アジャイルとウォーターフォールの強みを取り入れることで、品質とスピードの両立を図ることが可能です。
次項では、両手法を効果的に活用するハイブリッド開発の考え方と、活用シーンを解説します。
アジャイルとウォーターフォールを組み合わせる開発手法
ハイブリッド開発では、アジャイルとウォーターフォールの特性を目的やフェーズに応じて使い分けることが基本となります。
例えば、プロジェクトの上流工程では要件定義や設計を重視し、全体の構造を明確にするためにウォーターフォール型を採用します。
そして、下流工程にあたる開発やテストのフェーズではアジャイル型を取り入れて、短いサイクルで改善や仕様変更に柔軟に対応するなどの使い方が一般的です。
また、同じプロジェクト内でもチームごとに手法を分けるケースもあり、安定性と柔軟性を両立できる体制の構築が可能です。
このような組み合わせにより、計画通りに全体を進めつつ、変更やフィードバックにも対応しやすい開発体制を実現できます。
ハイブリッド型が活きるプロジェクト

ハイブリッド型の開発手法は、プロジェクトの性質や段階によって求められる進め方が異なるケースにおいて特に効果を発揮します。
例えば上流工程で要件を固めたうえで、素早いリリースなどの対応が求められるプロジェクトでは、ウォーターフォールとアジャイルの両方のメリットを活かすことが可能です。
また、開発メンバーのスキルレベルや体制が異なる場合にも、柔軟な手法の組み合わせが有効です。
全体を計画的に進めながらも、実装段階では現場の裁量を活かして開発を進めることで、品質とスピードのバランスが取りやすくなります。
変化に強い体制を構築したい企業や、プロジェクトごとに適切な進め方を選びたい現場にとって、ハイブリッド型はとても実用的なアプローチといえるでしょう。
プロジェクトの特性に応じて、柔軟に手法を組み合わせて進めることができるハイブリッド型の開発は、働くエンジニアにとっても大きなやりがいと成長機会につながります。
もしハイブリッド型の開発に取り組み、スキルを磨きたい方がいましたら、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーにご相談ください。
私たちテクニケーションでは案件選択制を採用しており、自分の伸ばしたいスキルや経験に合わせた案件への挑戦が可能です。
さらにチーム制を採用しておりベテランエンジニアからのサポートを受けられるため、ハイブリッド型の開発が未経験の方でも、案件に取り組むことができます。
手法に縛られず柔軟な現場で経験を積み、ご自身のスキルを磨きたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。
簡単30秒!
専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!
アジャイル開発とウォーターフォール開発のどちらがよいか迷ったら

アジャイル開発とウォーターフォール開発は、各々が異なる強みを持つ手法であり、どちらが優れているかはプロジェクトの内容や目的によって異なります。
要件が明確で安定した品質を重視する場合はウォーターフォールが適していますが、変化の早い現場やスピーディな対応が求められる場合にはアジャイルが効果的になります。
判断に迷う場合はプロジェクトの規模・期間・予算・メンバー構成などの要素を総合的に見て、自分のスキルや志向に合ったスタイルを選ぶことが重要です。
そして、開発手法の選択に迷ったときこそ、自分に合った働き方を見直すチャンスです。
もし、ご自身の今の開発スタイルに悩みを抱えていることがありましたら、ぜひ一度テクニケーションの専門アドバイザーにお話しください。
私たちテクニケーションでは、エンジニア自身が目指すキャリアや、ライフスタイルに合わせて案件を自由に選べる案件選択制を採用しています。
多様な開発スタイルの案件に挑戦できるため、自分の目的やスタイルに合った現場で経験を積むことが可能です。
また、会社間の案件単価に応じて報酬がアップする単価給与連動制も採用しており、実力のあるエンジニアほど高収入を得やすい環境も整っています。
会社間の単価はエンジニアに開示しているため、透明性の高い環境でモチベーションを保ちながら働けます。
さらに資格支援制度やチーム制を導入しているため、継続的にスキルアップができる環境です。
現状の働き方や目指すキャリアに迷いがありましたら、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。自身が輝ける環境を一緒に見つけていきましょう。
簡単30秒!
専門アドバイザーに相談する
履歴書はもちろん不要。今のメンバーも
みんな最初は雑談からでした。
ぜひお仕事以外にも趣味や
好きなことのお話で繋がりましょう!





















