「なぜエンジニアは“報われない職場”に残ってしまうのか?」
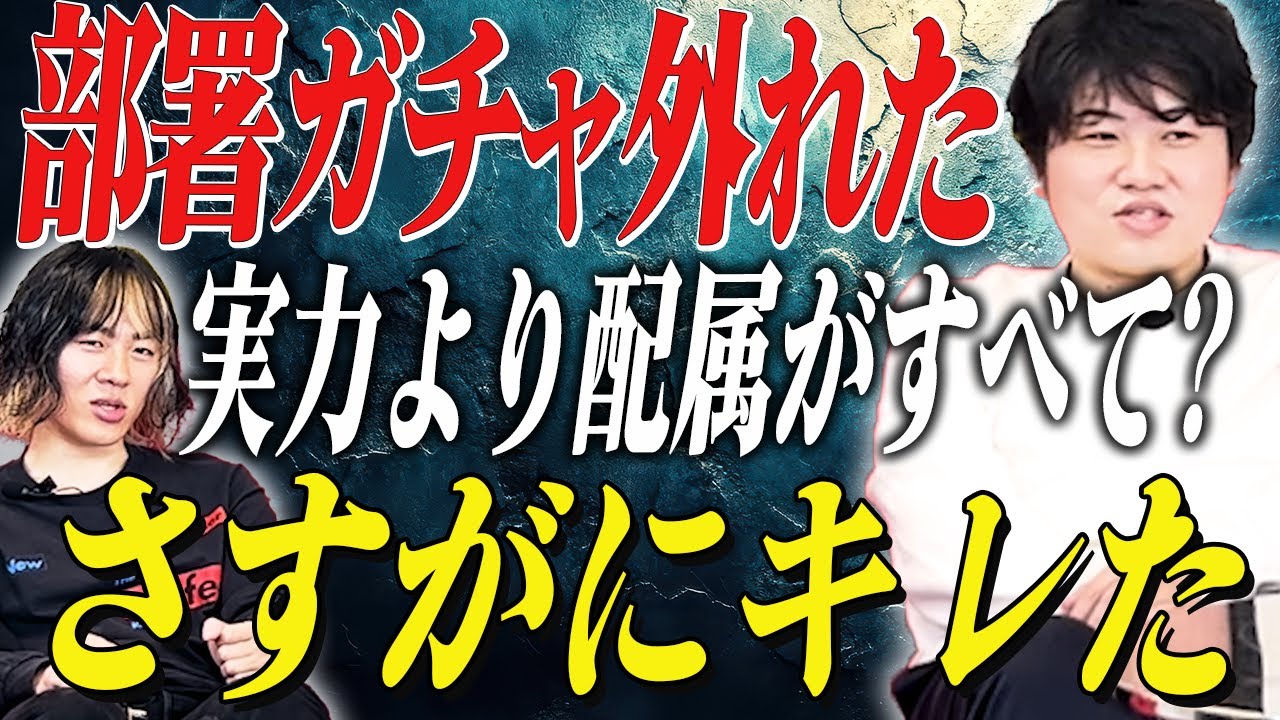
目次
はじめに
エンジニアとして働く中で、「頑張っているのに正当に評価されない」という悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。今回は、実際にそのような環境から転職を成功させたエンジニアの体験談をご紹介します。
転職のきっかけ:コロナ禍での理不尽な体験
待機者が続出する中で稼働し続けたにも関わらず
転職を決意したのは入社2年目、2020年のコロナ禍でした。当時勤めていた会社では1000人規模の組織で100人以上が6ヶ月近く待機状態となる深刻な状況でした。
そんな中、私は一度も途切れることなく稼働を続け、お客様からも高い評価をいただいていました。しかし、6ヶ月間待機していた同期が昇格し、給料が上がったのです。
部署間格差という名の不公平
なぜこのような理不尽なことが起きたのか。それは「部署間格差」でした。
- 開発部門:比較的評価が緩い
- インフラ部門:評価が厳しい
同じ会社、同じ同期でありながら、配属された部署によって待遇が大きく変わる。これは明らかに歪んだ制度でした。
努力が報われない評価制度の実態
実績を上げても評価されない矛盾
その後、私は着実に実績を積み重ねました:
- 単価の向上
- 4人の増員獲得
- お客様からの高い評価
これらの成果にも関わらず、昇格も給与アップもありませんでした。
目標設定シートという名の後出しジャンケン
特に問題だったのが「目標設定シート」の運用でした。
当初設定した目標(資格取得)を達成したにも関わらず、評価の段階で「それだけでは不十分。もう一つ別の試験も受けて合格しないと評価しない」と後出しで条件を追加されました。
これは完全に後出しジャンケンであり、評価者のさじ加減でいくらでも操作できる制度の典型例でした。
転職への決断
限界を迎えた瞬間
複数の理不尽な体験を経て、ついに限界を迎えました。上司に対して率直に意見を伝えました:
「納得がいかない。説明してほしい。それができないなら、課長に昇進させるか、別の部署に移動させてほしい。最悪、給料はそのままでも構わない」
社内異動という一時的な解決
幸い、理解のある部長のいる部署への異動が実現しました。新しい部長は私の実績を正当に評価してくれ、課長への昇進も果たすことができました。
しかし、根本的な問題は解決されていませんでした。評価制度そのものに問題があり、評価者によって結果が大きく左右される構造は変わっていなかったのです。
転職後の環境との比較
本質的な評価軸の重要性
転職先では、目標管理制度ではなく、より本質的な評価軸が採用されています:
- お客様への貢献度
- 単価の向上
- 実際のビジネス成果
資格取得は推奨されますが、それよりも実務での成果が重視されます。これにより、エンジニアは本来の業務に集中でき、無駄な評価作業に時間を割く必要がありません。
チーム全体での成長
現在の職場では、チーム全体が同じ方向を向いて成長できる環境が整っています。案件選定の際も「今後の増員につながるか」という観点で戦略的に考え、実際に2名体制から着実に拡大を続けています。
まとめ:転職を検討している方へ
もし現在の職場で以下のような状況に直面している方がいれば、転職を検討することをお勧めします:
- 努力と成果が正当に評価されない
- 評価制度が不透明で、評価者のさじ加減に左右される
- 部署やタイミングによって待遇が大きく変わる
- 本質的でない業務(無意味な目標管理など)に時間を取られる
エンジニアとしてのスキルと実績があれば、必ず正当に評価してくれる環境は存在します。現在の環境に我慢し続ける必要はありません。
自分の価値を正しく理解し、それを評価してくれる組織を見つけることが、エンジニアとしてのキャリアアップには不可欠です。





















